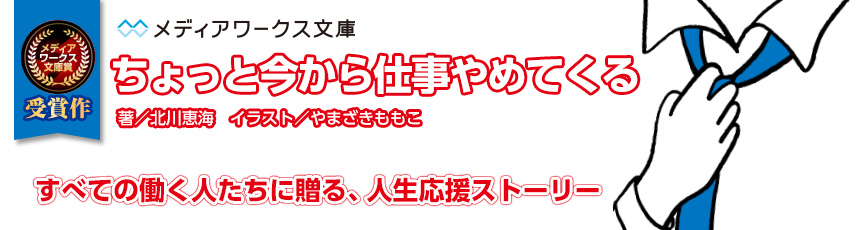十月十日(月・祝)
今日は朝からいい天気だ。
以前は、休日の午前中に起きるなんてことはなかった。太陽の光を浴びて、ゆったり伸びをすることもなかった。
シャワーを浴び、新しく買ったシャツに腕を通す。鏡の前に立ち、髪にワックスを揉みこみ、毛先を少し遊ばせる。
『休みの日こそ、気合を入れてお洒落をしろ』
ヤマモトに言われたことだ。
『たとえ、デートの相手が男であっても』
最初は、面倒くさいこと言う奴だな、と思った。が、いざそれを実行してみると、いつもより少し早めに起きて身支度を整えるだけでも、気持ちが上向きになることに気がついた。
お洒落と言われても着る服がないので、時間を見つけては買い物に行くようになった。
営業の外回り中に、ショーウインドウを見ながら歩くようになった。ガラスに囲まれた小さな世界はいつもカラフルで、見るだけで季節を感じることができた。店員の服装を見て、その時の流行も少しだけわかるようになった。高いものではなくても、新しい服を買うという行為は思っていたより楽しく、少しずつ、自分が好きな色や形もわかってきた。面倒くさかった美容院にも行った。
服装が変わると気分も変わる。気分が変われば表情も変わる。
辛気くさい顔をした奴と話したい、ましてや何かを買いたいと思う人はいない。という事に気づいたのはつい最近だ。
実際職場で、雰囲気が変わった、と言われるようになり、営業の成績が少しだけ上向きになった。
本当にほんの少しずつではあるが、仕事に対しても自信が出てきた。
小走りで改札を抜けると電車に飛び乗った。約束の時間ギリギリだ。
残念ながら、デートの相手は今日もヤマモトだ。
あれから毎週末ヤマモトに会っている。先週は俺の好きなサッカー観戦に行き、ほんのおとついは買い物をして、その後ヤマモトの好きな映画を見に行った。平日でもたまに仕事帰りに飯を食ったりする。まるで付き合いたてのカップルだ。
先日会った時、ヤマモトが俺に「何の仕事してるねん」と訊いた。
俺は〝営業〟だと答えると、ヤマモトに自分の名刺を一枚渡してやった。
それからヤマモトは、俺にさまざまなアドバイスをくれるようになった。
それはほんの些細なことから、直接仕事に関わりそうなことまで多岐にわたった。
ネクタイの色を少し明るくしたらどうか、とか。髪を切って耳とおでこを出せ、とか。
はたまた、誰かに何かを説明をする時は自分で思う一.五倍ゆっくり話せ、などということまで。
「でも、あんまりゆっくり話したら、馬鹿にしてると思われないか」
半信半疑な俺に、ヤマモトは得意の歯磨き粉スマイルで言い切った。
「絶対、思われへん! 保障したるわ」
「そうか?」
「あのな、大人って言うのは、たとえ相手の話が理解できへんかっても、よう『わからんかったから、もう一回言ってください』て言われへん。カッコつけーな生き物やねん。だから、小学生相手にするくらい、親切丁寧にゆっくり話してやるんが丁度いいんや」
「なるほどな……」
「もし、それぐらい知ってるわって怒られるのが怖かったら、頭に『ご存じかもしれないですけど、念のため』て言うといたらええんよ。そしたら、知ってることは向こうから自慢げに言うてきよるから。そしたら、『あー凄いですねえー、やっぱりよくご存じですねー。僕より詳しいんちゃいまっかー』言うとくねん」
その言い方が可笑しくて、俺はニヤニヤ笑った。
「適当すぎるだろ」
「言い方は東京風に変えとけよ? でもホンマやで。ちょっとでも相手を褒められるチャンスがあれば、何でも褒める。こっちの話を聞いてもらう前に、相手の話を聞く。相手に話を振る。そしたら、向こうもちゃんと聞く耳もってくれる。それで初めて対等な人間関係が築けるんや」
俺はヤマモトのミニ講座に感心しつつ、まだ訊いていなかった疑問を尋ねた。
「そういや、ヤマモトって何の仕事してるの?」
「今? 今はただのニートや」
「ニート! ってお前、仕事してないの?」
どうりでいつ誘ってもホイホイ来るわけだ。
「一応、アルバイト的なことはしてるで? 食い扶持は稼がんとな」
「大丈夫かよ、それで。今、就職先探してるってこと?」
「就職先……まあ、就職なんてせんでも、意外と生きていけるからな」
あっけらかんと答えるヤマモトだったが、もしかしたら何か事情があるのかも知れない。これ以上、そのことについて深く訊くのはやめようと思った。
「俺、営業か販売職かと思ったよ」
「そら、なにわの商人の血が流れてるさかい」
ヤマモトは俺でも変だとわかるほど、コテコテな大阪弁で言った。
「いや、血は東京じゃないのかよ。元はこっち生まれだろ?」
「親が元々大阪やさかい」
「そうだったんだ」
「嘘やさかい」
「えっどっちだよ!」
「なにわの商人なめたらアカンで、ちゅーこっちゃ」
「もう、わけわかんねーよ」
俺が呆れて笑うと、ヤマモトは嬉しそうにへへっと鼻をこすった。
どれが嘘で、どれが本当なのか。ヤマモトが、どこまで真剣に俺にアドバイスをくれているのかは、正直わからない。
しかし、間違いなくヤマモトの何気ない言葉は、少しずつではあるが、俺を変えていってくれている。仕事にもよい影響を与え始めている。
ヤマモトがあの日、あのホームで俺を見つけてくれなかったら、俺は今頃どうなっていたのだろう。
考えると恐ろしくなる。
それにしても、いくら顔が変わっていないとはいえ、小三の頃の同級生をよく見つけたものだ。
それをどうしても不思議に思い、ヤマモトに訊いてみた。
ヤマモトは、ちょっと気持ち悪いこと言っていいか、と前置きした後で、こう答えた。
「ビビッときてん。運命やったんかもな」
そしてニカッと笑った。
俺は、もうそれでいいか、と自分を納得させた。
偶然起こった奇跡のような再会。
それが俺たちの運命だったとしたなら、それでいいじゃないか。
そのおかげで俺は救われた。神様が見てくれていたのかもしれない。
俺はその数奇な運命に、素直に感謝した
一週間の歌 作詞作曲 青山 隆(たかし)
月曜日の朝は、死にたくなる。
火曜日の朝は、何も考えたくない。
水曜日の朝は、一番しんどい。
木曜日の朝は、少し楽になる。
金曜日の朝は、少し嬉しい。
土曜日の朝は、一番幸せ。
日曜日の朝は、少し幸せ。でも、明日を思うと一転、憂鬱。以下、ループ
入社一か月目にして、現実逃避のために作った歌だ。いつまでたっても俺は阿呆だ。
今日は、水曜日。一週間の折り返し。つまり、身体はそこそこ疲れてきたのに、まだ半分も週が残っているという、個人的には一番モチベーションを保ち辛い曜日である。
しかし、今日だけは朝から気合いが入っている。
先週ヤマモトに選んでもらったネクタイを、鏡の前でいつもより丁寧に締めた。澄みきった秋空のような美しいブルーだ。
入社してからずっと通い詰めていた小谷製菓という菓子メーカーで、少数ながらも受注を取れそうなところまできていた。今回の受注は、社内広報的な小さいものだが、これが上手くいけば、チョコの中に入れるフレーバー説明書をうちで印刷できるようになるかもしれない。一度契約にこぎつければ、今後かなり重要なマーケットとなる。入社以来、最も大きな契約がまとまる可能性があった。
「おはようございます!」
一番乗りだと思ったオフィスには、五十嵐先輩の姿があった。この部署のエースとも言える存在で、みんなから一目置かれている。俺の憧れの人だ。顔も良ければ人間性も素晴らしい。入社以来、俺の面倒をよく見てくれていて、数少ない話しやすい先輩の一人でもある。
「朝から元気だなあ」
五十嵐先輩は、端正な顔立ちを崩さぬまま、いつもの優しい笑顔で言った。
ピンクに近いような薄紫色のネクタイが良く似合っている。
そういえば先輩はいつも、明るい色のネクタイをしている。話すスピードも、この部署の誰よりもゆっくりだ。ただでさえ早口な人間が多い中、先輩から漂う余裕や優しさは、話すスピードが関係しているのかもしれない。
「今日はちょっと、気合いを入れて臨まないといけないので」
「小谷製菓とのアポか。どうだ、いけそうか?」
「なんとか、いい感じにいけそうです。今、万全の準備をしている最中です」
「そうか。最近、調子良さそうだもんな。これが決まればデカいぞ。わからないことがあったら、何でも聞けよ」
「はい! ありがとうございます」
これが上手くいけば、大きな自信になる。それを応援してくれる実績ある先輩もいる。これほど頼もしいことはない。
今回だけは、上手くいく気がする。
どんなに辛い仕事でも、どんなに体力的にキツくても、成果が出れば精神的に楽になる。病は気からとはよく言ったもので、精神状態が安定すると、不思議なほど身体が元気になる。残業なんてなんのその。
部長の怒鳴り声だけは相変わらずだったが、それでもヤマモトに愚痴を聞いてもらえることで、ストレスも格段に減った。
今の俺は、よいサイクルに入っているという実感があった。
俺は意気込んで、小谷製菓に出向く準備をした。
「それで、今日は上手いこといったんか」
初めて二人で飲んだあの居酒屋で、俺たちは再び膝を突き合わせていた。店の名前と同じように、今日も客入りは〝大漁〟だった。
早く今日の結果を報告したくて、帰りにヤマモトを呼びだすと、ヤマモトは二つ返事で来てくれた。
「うん、かなりいい感じだった。担当が野田さんっていうんだけど、俺が入社した当時から話を聞いてくれている人なんだ。て言っても最初はなかなか難しい人だったんだけどさ。ちょっとずつ話を聞いてくれるようになって、最近ではプライベートの話をしてくれたり。あっ、先月お孫さんが産まれたんだって。その子がチョコを食べられるようになるまでは現役で頑張りたいって……」
言いながら俺はハッとしてヤマモトを見た。
「ごめん、一人でしゃべって」
「ぜんぜん、ええよ。それで?」
ヤマモトは優しい微笑みで言った。
「それでさ、とうとう俺の誠意と熱意が伝わった、って言ってくれて。まだ少数だけど契約を結べたんだ」
「よかったなあ」
ヤマモトは嬉しそうに目を細めた。
「これが上手くいけば、いよいよ次は大きな単位の受注を取れるかもしれない」
俺は饒舌だった。
「すごいやん。このまま上手いこといったらええな」
まるで自分のことのように嬉しそうに笑うヤマモトを前に、俺は小さな座布団の上でモゾモゾと尻を動かし、できるだけ姿勢を正した。
どうしても、ヤマモトに伝えたいことがあった。
ピンを背筋を伸ばして、目の前の男をまっすぐ見つめると、彼は不思議そうな顔をした。
「ヤマモト、色々ありがとな」
ヤマモトは意表を突かれたような、驚いた表情を浮かべた。
そして、少し照れくさそうに言った。
「なにがやねん」
「ヤマモトがいてくれなかったら俺、この契約取れなかった」
ヤマモトは、はにかんだ笑みを浮かべたまま、ビールに手を伸ばした。照れくささを隠したいように見えた。
「なに言ってんねん。今までの努力と誠意の賜物や。青山の実力やで」
「いや、俺を変えてくれたのはヤマモトだよ。自信を持って相手と話をできるようになったのも、ヤマモトのアドバイスがあったおかげだから。マジで、感謝してる」
真面目に話す俺に対し、ヤマモトは、ハハッと声を出して笑った。
「なんや、酔っぱらってんのか?」
「まだ酔ってねえよ」
俺が微笑みを返すと、ヤマモトがさらに嬉しそうに、ニカッと笑った。
出会った時からちっとも変わらない、この笑顔。
俺の笑顔はどうだろう。少しは自然に笑えるようになっただろうか。
ヤマモトから見た俺が、ちょっとでも変わっていたらいい。
いつか、こいつの笑顔は素晴らしい、と思ってもらえるような人間になりたい。
ヤマモトからも、周りの人からも。
上機嫌で二杯目のビールを飲み干した頃、ヤマモトが言った。
「青山、かなり残業続いてるんやろ? 今日はそろそろ解散しよか」
「えーもう?」
「いま身体壊したら、元も子もないやろ?」
腕時計に目をやる。
時刻は既に、午後十時をまわっていた。
「契約決まったら、改めてゆっくり祝勝会でもしようぜ」
そう言うと、ヤマモトはもう一度、ニカッと笑った。
「まあ、そうだな。あっ、今日は俺が誘ったからな」
俺はひったくるように伝票を手に取ると、急いでカバンの中の財布を探った。
店の外に出ると、少し風が吹いていた。冷たさを増した風が、ビールで少し温まった頬をなでていく。とても気持ちがいい。
ヤマモトも気持ちよさそうに、風に短めの髪をなびかせていた。
「今日は、ごちそうさん。ほんなら祝勝会は、俺がどっかいい店連れてったるわ」
「マジで? よっしゃあ! 期待しとこ」
「ほな、明日も適度に頑張れよ」
ヤマモトはそれだけ言うと、くるりと背を向け、歩き出した。
「おう! ありがとな」
俺はその背中に向かって言った。
ヤマモトは背を向けたまま、片手を上げて応えた。
本当に気持ちのいい風だ。俺はゆっくり歩きながら思った。
四季の中で秋が一番好きだ。暑くも寒くもなく、花粉も飛ばない。
そして何より、柔らかく吹くひんやりとした風は、心を穏やかにさせる。
俺は、このまま何もかもが上手くいくと信じていた。
十月十五日(土)
ヤマモトの言った通り、このところ残業続きだった。
以前に比べると格段にやる気はあるが、それと体力はまた別問題。気張っていても実際、辛い。
どんなに踏ん張り時でも身体を壊しては元も子もない。まったくその通りだ。
明日は日曜。ゆっくり眠って体力を回復しよう。そう思った俺は、いつもより少し早めに仕事を切り上げ、足早に家へと向かった。
自宅のある駅に着いた途端、タイミングを計ったかのように携帯が鳴りだした。
一瞬、部長の顔が頭をかすめて、身体がビクッと反応した。
恐る恐るポケットから携帯を取りだし、表示された名前を見て、また違う意味で驚きを覚えた。
――もしもし?
――ああ、俺、岩井だけど。
――おーおー、この前はありがとうな。
――あーそのことなんだけどさ。あの電話の後、なんか妙に気になってさあ。
――ん?
――ちょっと訊いてみたんだよ。いろんなヤツに。
――何を?
――ヤマモトケンイチだよ。
――あっああ、それなら……。
もう大丈夫だよ、と言おうとした瞬間、岩井の口から思いもよらない言葉が発せられた。
――あいつ今、ニューヨークにいるんだってよ。
即座に理解できず、数秒間言葉を失った後、俺は声を振り絞った。
――……えっ?
――だから、ニューヨーク。ケンイチのやつ、今ニューヨークで舞台関係の仕事してるんだってさ。すごくね?
――今って、今現在ってこと? 日本に帰ってきてるとかは?
――いいや? だって訊いたの昨日だし。今は舞台の真っ最中らしいぞ。そんなに目立つ感じの奴じゃなかったから、びっくりしたよ。でも今思えば、あの頃からなんかみんなとは違うっていうか、なんか大人っぽくてさ。アーティスト系の才能とかあったのかな。
――えっ、今、今、ニューヨークにいるんだよな?
――だから、そうだって。
――そうか……。
――隆、ケンイチに何か用事だったのかなーと思って連絡したんだよ。もし連絡先が知りたいなら教えるけど?
――いや、いや、もう大丈夫だ。
――そうか。ならいいんだけどさ。
混乱した脳内を一刻も早く整理したい。俺は会話を締めにかかった。
――それで連絡くれたのか。わざわざ悪かったな。
――いや、それは全然いいよ。あーあとー、またみんなで飲みにでも行かないかと思って。ほら、幹生とか最近連絡取ってる? 今回、あいつにケンイチのこと訊いたんだけどさ。久しぶりに電話したよ。
――ああ、俺もしばらくとってないな。
――せっかく隆とも久しぶりに連絡とれたしな。
――うん、そうだな。いきなりだったけど。
――はは、確かに。いきなり過ぎてちょっとビビったわ。でも、電話くれて嬉しかったよ。就職してからは特に、昔の仲間と集まる時間もなかったしな。
岩井の声からは、寂しさが伝わってきた。
どうやら、わざわざ連絡をくれたのは、ただヤマモトの現状を知らせたかっただけではなかったようだ。
――それは、俺も同じだよ。
――今、仕事忙しいの?
――今はちょっとな。ちょうどバタバタしてて。
――そうか。じゃあ落ち着いたら、またみんなで時間合わせようぜ。マジで。
――そうだな。落ち着いたら一回集まろう。
社交辞令ではなく、俺は心からそうしようと思った。
夜通し語り合った中学生の頃が、懐かしく頭をよぎった。
――なあ、一樹。
――ん?
――四葉の営業って、キツイ?
――あーあ、ヤバいね。ま、なんとか沈まないように、もがいてるけどな。
――そうか…………みんな大変だよな。
――そうだな。人生ってヤツは、なかなか大変だよー。
――はは。
――じゃあ、また。
――おう、またな。マジで、連絡するから。
――おう! 待ってるわ。
電話を切った後、様々な気持ちが体中を交錯していた。
みんな同じだ。苦しんで、もがきながらも、なんとか自分の道を見つけようと模索している。
岩井……、一樹だって、大きな企業になればなるほど、しがらみやプレッシャーが巨大になって圧し掛かってくるだろう。
この契約の件が落ち着いたら、みんなで飲もう。
会社に対する愚痴を言い合って、社会に対する不満をぶつけて、格好つける必要なんてない。たまたま近くの席に座った、デカい面した人生の先輩方に『最近の若者は……』と、陰口叩かれるくらい、大声で話してやろう。
それにしても――――
俺は宙を見据えながら思った。
ヤマモト。
あいつは、俺の同級生のヤマモトケンイチではない。
では、アイツは一体、誰なんだ。
どうして、俺の前に現れたんだ。
出会ってからずっと、なぜこんなにも、俺のことを助けようとしてくれている。
わからないよ。
ヤマモト――――
お前は一体、何者だ。