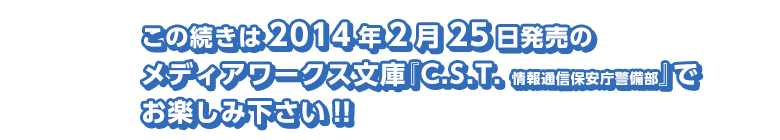◇◆◇
CSTは現在、六部隊編成である。
創設当初は四部隊で、第一部隊から第三部隊までは捜査、第四部隊は解析と不正プログラム対策を担当していたらしい。業務の拡張に伴い、第五・第六部隊が増設された。組織の改変で細かい担当業務の変更は何度かあったが、主に第五部隊が要人警護と調査、第六部隊が地方支部のバックアップを、それぞれ担当している。
入隊当時、伊江村が配属されたのは第五部隊で、着任時の挨拶の際に森に言われた。
「一応、慣例に従って班長、副隊長ってステップは踏むことになるだろうけど、君はすぐ隊長になるだろうから、そのつもりで上官の仕事のやり方を見ておきなさい」
伊江村はそのとき、自分にはコミュニケーション能力が欠けている、部下を持つ立場には適さないと思う、というようなことを答えた記憶がある。森は困ったような顔をして言った。
「上官として、自分より優秀な部下を持つことほどやりにくいことはないって思わない? 先輩たちを困らせないためにも、君は早めに昇進するべきだ。コミュニケーションだってテクニックなんだから、ここで勉強しなさい」
十七歳の冬、降りかかる災いを振り払うためには力が必要なのだと知った。権力も力の一つには違いない。だから、勧められるままに試験を受けて昇進してきた。
昇進すると、自分の意見や都合が通りやすくなる。物事がスムーズに進む。異常に早い昇進は別の面倒も引き起こすし、伊江村にはいまだに、情保や隊長という地位が、自分のいるべき場所なのかどうかわからない。しかし、これまで自分の居場所だと思えたところなどなかった。結局、どこへ行っても同じなのだった。拗ねているわけではない。ただ、自分はそういう性質の人間なのだと思う。
「先週十五日から、関東地方の熱中症による死亡者数が急増している」
各隊の隊長と副隊長が集まった会議室で、警備部長の鷹岡が言った。制度上は情報通信保安庁長官が最高指揮官だが、実際にCSTを統轄しているのは警備部長だ。
「死亡者のほとんどが高齢者だ。十五日から昨日二十一日までの七日間で六百三十四件報告されている。年によってばらつきはあるが、熱中症による死亡件数は、五月から九月の五か月で多くて二百人といったところだ。一週間で、しかも高齢者だけで六百人超えというのが異常だというのはわかるだろう」
ビーンズ経由で配布された資料を見ると、死亡日時と生年月日、年齢、住所を一覧にしたリスト、日時別、年齢別に件数を集計したデータが記載されている。
「なんでうちにこんな話が来るんだ。福祉保健局の管轄だろうが」
発言したのは第一部隊隊長の荒垣である。第五部隊の森とともに鷹岡とは同期なので、階級は下でも口調に遠慮がない。
「率直に言うと、BMIを介したウイルスが原因の可能性がある」
鷹岡が隣に座った男に目をやった。
スーツを着た四十代と思われる男が立ち上がり、一礼して東京都福祉保健局の者だと名乗った。
「熱中症は高温下での運動や労働のため、体内の調節機能に異常をきたす高温障害です。今回の六百三十四件はいずれも熱中症の症状を呈しています。しかし、通常、最高気温三十度を超えたあたりから死亡が増え始めますが、死亡件数が急増し始めた先週は雨の日が続いていて、最高気温も二十四度に留まっている。ご存じの通り、関東の高齢者の多くは、〈関東あんしんネットワーク〉に登録しています。ビーンズで体内をスキャンしていて、異常が発生すれば消防機関に連絡がいく仕組みになっている。この一週間の事例は、連絡が入った数分後に生体反応がなくなっていることが多いのです。進行があまりにも早すぎる。何らかの病原体が原因になっている可能性も考えましたが、検出されないので、コンピュータウイルスの可能性を検討していただきたいのです」
解析を担当している第四部隊隊長の岡田が口を開いた。
「〈関東あんしんネット〉経由でマルウェアが拡散した可能性を考え、サンプルとして死亡した二十人のビーンズを解析しました。自動削除の設定がされていたのか、ファイル自体が残っていないものも多く、今のところそれらしいものは検出されていません」
岡田はコンピュータウイルスという呼称を使わず、必ず不正プログラム全般を指すマルウェアという呼称を用いる。「ウイルス」の定義が曖昧である、というのがその理由で、彼なりのこだわりらしい。
「自動削除設定」とは、脳や身体と接続しているビーンズの機能の一つだった。プライバシー保護のため、正式な手続きを踏まずに身体から外された場合、あるいは持ち主の生体反応がなくなった場合に、保存されていたファイルを自動的に削除するように設定しておくことができる。復元できるデータもあるが、完全な復元は困難だった。
部長が言った。
「アクセス可能な脳の部位は限られているし、強固なセキュリティもある。なにより、脳神経工学の専門知識がないとウイルスが作れない。それでこれまで大きな問題は起こらなかったが、人体への不正なアクセスはBMIが普及し始めた当初から危惧されてきたことだ。ウイルスの仕業でない可能性も含めて、検討してほしい。何か気づいたことはあるか?」
「ビーンズのOSはすべてBOXES社の〈エルピス〉ですね」
第二部隊隊長が言い、森が答えた。
「まあ、シェアを考えると不思議ではないけどね。国内のビーンズは八十%以上が〈エルピス〉だ」
リストにソートをかけてデータを並び替えていた伊江村は、口を開いた。
「〈資料3〉の年齢別分布は十歳ごとに集計していますが、六十四歳未満と六十五歳以上の死亡者数に大きな開きがあります。六十四歳未満は各年齢、多くても一桁ですが、六十五歳からは五十人以上と極端に増加している。しかも六十五歳の誕生日を迎えた当日に死亡している患者が八人。やはりウイルスでは? 〈あんしんネットワーク〉の登録者情報と照合して、六十五歳以上に発症するようプログラムされているのかもしれません」
ふうん、とうなるような声を出して、各人が資料を確認する。
「しかし、対象を六十五歳以上に限定したのはどうしてかな」
森の言葉に、伊江村は答えた。
「六十五歳以上を大量殺害すれば、高齢者問題は即座に解決です」
総人口における六十五歳以上の割合、すなわち高齢化率が二十一%以上になると、その社会は超高齢社会と呼ばれる。現在、日本の高齢化率は三十一%に達していた。高齢化と少子化はセットで進行することが多いため、若年層の社会保険料の負担は増大していた。そのうえ、政策は有権者の中で大きな割合を占める高齢者を偏重するものになっており、それが問題視されているところだった。労働力と、社会保険の財源確保のため、成人年齢は二十歳から十八歳に引き下げられていたし、就労年齢も下がっている。
伊江村の発言に、岡田が眉を寄せる。
「不謹慎だぞ」
「失礼しました」
伊江村はすぐに詫びたが、無表情で言ったので、隣にいた篠木の手に腕をつかまれた。「もっと申し訳なさそうな顔して!」と小声でたしなめられる。
岡田は腹立たしげな顔をして伊江村を見ている。いちばん歳の近い隊長だが、どうやら良く思われていないようだということは伊江村自身も察している。
「まあ、それは有り得るよね。最近、ネット上でもエキサイトしてるし」
森が隣に座った山上を見て言った。山上がうなずいて言う。
「国民年金の保険料引き上げが決まってから、強い反発が起こってます。通知が出てから、社会保険庁への意見書も爆発的に増えてますし」
「政治的な意図でつくられたウイルスである可能性は十分考えられるな。第四部隊は引き続きビーンズの解析を頼む。〈あんしんネットワーク〉の捜査は第二部隊に任せる。ウイルスであった場合、亜種が発生する可能性は高いし、別のところで類似の事例が発生するだろう。各隊、気になることがあれば報告してほしい」
鷹岡が述べ、会議は終わった。
伊江村が篠木と連れ立って席を立つと、会議室を出たところで声をかけられた。
「おい小娘」
振り向くと、荒垣が副隊長の相模を従えて立っていた。
改まった場ではさすがに「伊江村」と呼ぶが、いつもたいてい小娘呼ばわりだった。同じようにいつも小僧呼ばわりされている篠木が、不快そうな顔をする。
伊江村が黙って顔を向けると、荒垣が言う。
「なんでお前んとこの隊員が、うちの持ち場にいた」
東方見聞録のミニライブでの暴動の件だろう。御崎の提出した記憶データが隊長会議で共有され、そのときにも他の隊長から質問が出た。論点が別にあったため、そのときは「調査に行った途中で偶然通りかかった」という説明で済んでいた。
「大阪のソフトウェア会社から新製品のデータが流出しました」
使われていたPCの機種を挙げて、伊江村は言った。
「PCが海外で製造された時点で不正プログラムをインストールされていた可能性があるので、メーカーに確認に行かせていたのです。本社がライブ会場のすぐ近くで、なにやら騒がしいので見に行ったそうです」
流出事件があったのも、水元をメーカー本社に行かせたのも事実だった。流出の原因は外部メモリを媒介として仕込まれたバックドアプログラムだと、すでに突き止めていたが。
荒垣がじっと伊江村の顔を見て言った。
「まったく、顔色一つ変えないんだからな」
「顔色を変える理由がありません」
短く答え、伊江村は話題を変える。
「それより、あの暴動もウイルスが原因では?」
「御崎もそう言ってた。こっちで引き取れないか、警察に交渉に行ってる」
荒垣が答え、「うちの件だ、首突っ込むなよ」と釘を刺して去っていく。
「まったく、あのおっさんは、こっちが若いと思ってナメきってんですよ!」
伊江村の後について階段を下りながら、篠木が憤慨した口調で言った。
「実際、荒垣隊長にとっては、わたしもお前も子どもみたいなものだろう」
平淡な口調で伊江村は答える。最年少の隊長と歳の変わらない副隊長の組み合わせで、隊員も総じて若い。経験値が低いのは事実だった。
「わたしはあの人が好きだが……」
「えっ! 俺よりも!?」
篠木の発言を黙殺して、伊江村は続けた。
「あの人には裏表がない。最初に声をかけられた時、第一声は『五人殺してるそうだが、ホントか?』だった」
「……」
踊り場にさしかかった伊江村の顔を、篠木がちらりと見た。篠木も聞いているのだろう。荒唐無稽なようで、事実の含まれた噂を。
黙って階段を下り、隊室が見えてきたところで、篠木が怒ったような口調で言った。
「俺を試すのはやめてくださいよ」
◇◆◇
御崎が警察から帰って来ると、第四部隊の岡田から、「東方見聞録のライブで押収したビーンズの解析が終わった。解析室に来るように」とメールがあった。「(ただし浅井はよこすな)」という条件つきで。
浅井は岡田隊長のトラウマになっているのだろう。奔放すぎて理解できないに違いない。
松葉杖をついて、御崎が庁舎七階にある解析室まで行くと、先客があった。伊江村だった。広いテーブルを挟んで岡田と向き合い、座っている。珍しく、公然ストーカーの篠木がいなかった。
御崎の顔を見て、伊江村が口の端を上げて見せる。顔中にイライラを張り付けた岡田が、「そこで待ってろ」という意味なのか、御崎に壁際のテーブルを指さして見せる。
「君の部下を邪険にしたつもりはない。優先順位の問題だ」
伊江村に向き直り、岡田が言った。伊江村がうなずいて答える。
「抗議に来たのではありません。お忙しいのは重々承知です。できないとおっしゃるなら、うちでやります」
「挑発はよせ!」
「挑発ではなく提案です」
「昨日篠木が持ってきた案件もまだあるんだ」
「うちでベースを作ってそれを確認していただく形を取れば、お手間を取らせないと思います」
伊江村が淡々と話しているのに対し、岡田はどんどん苛立ちを濃くしている。
伊江村が班長、副隊長と異例のスピードで出世して、御崎が最初に心配したのは数少ない他の女子隊員との関係だった。母・姉・妹の三人によって、職場や学校での「女同士ってやだよね~!」的エピソードを聞かされ続けてきたので、伊江村が他の女子隊員から妬まれるのではないかと思ったのだ。
しかし、山上によると「最初は先輩がガタガタ言ってたけど、スペックがちがいすぎるのがわかって、もう出世の件ではやっかみの対象にもならない」し、おまけに「美人だ美人だ言われてるけど、愛想がなさすぎて篠木以外の男には全然モテない」ので、男をめぐるトラブルもまったくないのだそうだ。むしろ、やっかんでいるのは男のほうなのだという。特に出世で抜かれた、あるいは抜かれそうになっている地位の男にアンチが多く、岡田がその急先鋒というわけだった。
岡田と言い合っている伊江村を見ながら、まあ確かに、と御崎は思う。可愛げないもんな。無愛想だし。山上がボディタッチしながら「やだー岡田隊長の意地悪! お願い~」でなんとかしてしまうところを、伊江村は妥協案を探って生真面目に交渉してしまうのだ。
「明日の十一時までになんとかする!」
不本意そうな口調で岡田が言い、ありがとうございます、と丁重に頭を下げて伊江村が部屋を出ていく。頭をかきむしりながら、ボトルの水を飲み干し、岡田が呼んだ。
「御崎三保正!」
「はい」
御崎がテーブルにつくと、眼鏡を外して眉間を押さえながら岡田がため息をついた。全身からストレスの気配を立ち上らせている。彼にとっては、浅井と伊江村が天敵のツートップというわけだった。
岡田は童顔で背が低いので若く見えるが、確か、三十五、六歳だったはずだ。第五部隊に移った森に代わって、三十歳で第四部隊の隊長および解析室長になったと聞いている。伊江村が隊長に就任するまでは最年少の隊長だったらしい。重鎮である森の後任に抜擢されたのだから、優秀なのは確かだった。
リストを御崎の前に置いて、岡田が言った。
「それらしいマルウェアが検出された」
リストは、サンプルを押収した観客についてのもので、当選者向けページへのアクセス方法、当日の異常行動の有無、ビーンズから不正プログラムが検出されたかどうかを示していた。リストに目を通しながら、御崎は言った。
「さっき警察からこの件を引き上げてきました。警察の調べでは、暴れ出した連中に共通点はないということでしたが。ビーンズで応募した連中が多い、というだけで」
「解析でも、暴れた連中全員に共通するような原因は見つかっていない。見つかったマルウェアは、暴れていない連中のビーンズから検出されている。しかも、全員ではなく、一部だけだ。当選者向けページにマルウェアが仕込んであって、それを閲覧して感染したようだ。暴れ出したやつのビーンズにはすべて、あの暴動の直後、いくつかのプログラムが削除された形跡があった」
「同じように感染しても、発症する場合としない場合があったということですか」
「おそらく、ビーンズにこのマルウェアが感染した連中は、全員発症している。ただ、このマルウェア自体は、いたって普通のものだ。情報を盗み見ているだけで、暴動につながるような機能はない。削除されたプログラムを復元してみないと何とも言えないが、暴れ出した連中にはもう一段階、何らかの働きかけがあったのではないかと思う」
もう一枚リストを渡し、岡田は「もう行け」と言わんばかりに手を振った。
二枚めのリストは、ウイルスの機能を挙げたもののようだった。入力情報を取得し、スクリーンに表示している内容を盗み見ることができるようだ。
当選者は、当選者向けページをビーンズで閲覧した者と、PCで閲覧した者に分かれる。携帯電話から閲覧した者もいたが、これは一桁で、少数派だった。暴れていた連中には、ビーンズで閲覧した者が圧倒的に多い。PCで閲覧した者も、そのPCに接続すればビーンズがウイルスに感染する。このウイルス自体に暴動を引き起こす要素はないが、情報を盗み見て、発症させる人間を選別し、あらためて別のウイルスを仕込んだという可能性もあった。
松葉杖をつきつつ、リストに目をやりながらドアを開けると、廊下に伊江村が立っていた。御崎は動揺してリストを取り落した。
伊江村が身を屈めて、床に散らばったリストを拾い上げた。リストを揃え、御崎の胸のポケットにクリップで留める。よく見ると、プラスチック素材のクリップはうさぎの形をしていた。
「骨折すると不便だな。治るのにどれくらいかかる?」
伊江村が御崎の顔を見上げて訊いた。
「早くて二週間」
黒目がちの瞳にまっすぐ見つめられて、胸の中がざわざわした。
並んで歩きながら、伊江村が言う。
「浅井に取りに来させればいいのに」
「『浅井はよこすな』って注文がついてたんだよ」
「岡田隊長から?」
「ストレス源だからな」
「熱中症の話、荒垣隊長から聞いたか?」
「聞いた。ライブの件も、ウイルスっぽいな」
他に誰もいないので、伊江村の声も表情も柔らかかった。肩肘張っているようには見えないが、やはり「隊長」でいなければいけないときはそれ相応の振る舞いがあるのだろう。情保学校時代からの同級生だし、同期が相手だと気楽なのだろうと思う。
廊下を歩きながら、伊江村は横からしきりに御崎の顔を見上げては視線をさまよわせて、そわそわしていた。
待っていたのは何か言いたいことがあったのだ、と思い当たり、御崎は訊いた。
「何?」
自分でも気持ち悪いと思うくらい優しい声が出た。
「……こういうときにどう言ったらいいのか、よくわからないんだが……」
落ち着かない様子で、持っていた資料を丸めながら、伊江村が言いよどむ。
伊江村が恥ずかしがってもじもじしているのを見ると、御崎は二歳になる姪っ子を見ているときと同じ気分になる。何か菓子買ってやろうか? と言いたくなるような。
意味もなく資料の端に折り目をつけながら、伊江村が口を開いた。
「ある社会学者がコラムで書いていた。現代日本人が一生のうちで接点を持つ人間の数は、インターネット上での接触も含めると、平均三万強なんだそうだ」
「……うん?」
「親密な人間関係を築く相手は学生時代の方が多くなる傾向があるそうだが、社会に出てからだって新しく接触する人間は多い」
「……」
「出会った人間のうちの〇・一%がそういう相手になり得るというから、これから出会う人間の中で、新しくそういう相手が出てくる可能性は高いと思う」
「……」
歯切れ悪く言い募る伊江村の言葉を聞いているうちに、話が見えてきた。
山上の含み笑いが思い浮かぶ。「御崎が彼女にふられたんだってー。励ましてやってよ」とかなんとか、言ったのだ。伊江村は学生時代からなぜかこの手の話を忌避しているので、困ったのだろう。「励まし」の根拠を探したのに違いない。
「――わかった」
大仰にうなずいて、御崎は言った。
肩の荷が下りたのか、伊江村は安堵したように、BMIが普及し始める前に脳神経工学の分野でブームになっていたという研究について話し出した。もともとBMIは医療分野で使われ始めたもので、脊髄損傷や脳卒中により身体が麻痺した患者の脳に思考によって電気信号を送り、身体を動かすことを可能にした。脳に作用する何らかのプログラムを送り込めば熱中症やせん妄に似た症状を引き起こすこともできるはずだ、というのだ。
伊江村は、さっきとは打って変わって饒舌だった。御崎の顔を見上げながら、目を輝かせていた。性質が基本的にオタクなんだろうと思う。
気にかけていてくれたことはうれしいが、俺の悩みは、この先新たな出会いがあるかどうかなんてことじゃない、と御崎は思った。学生時代から好きな女の子を口説くこともできず、あきらめることもできず、その女の子にどこかの学者の説まで用意して「他にもいい人いるよ」と慰められてしまったことだ。
◇◆◇
情保学校二年生の冬休み、十七歳の御崎は静岡の実家には帰らず、学校の寮で大晦日を迎えた。
男子寮では、情報通信保安官の上級試験を受験する二年生が、実家に帰らず翌年五月の試験に向けて寮で勉強に励む「合宿」と呼ばれる風習があって、それに参加するという名目だった。冬休みの間、毎日自習室に籠ってひたすら勉強し、夕食後には一斉に予想問題を解かされて、それについて復習するという修行僧のような生活を送るのだ。
浅井は「僕、そういうストイックなのは無理。年末年始にだらだらしなくて、いつするっていうのさ?」などと言って、いつもだらだらしているくせに、終業式の日に早々に実家に帰って行った(それであっさり合格していたのだから、腹立たしいことこの上ない)。
大晦日の夜、十九時から「息抜き」と称した宴会が始まるのも毎年恒例だった。それまでの禁欲的な生活の反動なのか、全裸で廊下を走りまわったり、踊ったり歌ったり、頭がおかしくなったとしか思えないバカ騒ぎが起こる。
寮のたがが外れたような狂乱の中、御崎はどうも落ち着かなかった。酒を飲んでも気持ちは高揚せず、気持ちは完全に置いてきぼりを食っていた。夜のランニングが習慣になっていたので、気分転換がてら走りに行こうとしたが、外は雪だった。特にあてもなく、ダウンコートを着込んで外へ出た。
刺すような冷たい夜の空気の中、雪がしんしんと降り積もっていた。街灯の青白い光にところどころ照らされながら、あたりは異常とも思える静けさに覆われていた。時折、自動車が雪を踏みながら通りかかり、遠ざかっていった。
暗い住宅街の道を向こうから歩いてくる人影があって、見覚えのあるその白いコートと淡いグリーンのマフラーを目にしたとき、「しまった」と思った。同級生の伊江村だった。
こちらに気付いたらしく、確かめるように大きな目でまばたきをして、少し首をかしげるようにしていた。マフラーをぐるぐると首まわりに巻いて、イヤーマフラーとミトンの手袋で完全防備、着ぶくれていた。
「何してんだよ」
御崎は立ち止まって声をかけた。口調がつっけんどんになった。うろたえていた。
伊江村が黙って両手をコートのポケットに入れ、ミトンの手袋をはめたまま何かを引き出す。「おしるこ」と書かれた缶が二本。
「寮の自販機にはないんだ」
伊江村が言った。
そういえばこいつ、冬になってからいつも昼に食堂でぜんざい食ってたな、と思い出した。山上に「野菜とか肉も食べなさいよ!」と子どものように怒られているのを目撃したこともある。
「山上は?」
「宮崎に帰った」
訊かなくても知っていたが、話すことがなかった。
伊江村織衣はその年の四月に、二年生に編入してきた同級生だった。
高校や大学を卒業してから情保学校に入り、飛び級で二年次に編入してくる者はいたが、中学からストレートで入学して飛び級になることは珍しかった。それだけでもセンセーショナルだったが、伊江村の外見は噂の種になりやすかった。彼女を初めて見たお調子者の同級生の第一声は「美しいなァ……」だった。「可愛い」でも「美人」でもなく、十代の男が日常会話で使うことのない「美しい」という単語が出てきたところが象徴的だった。
つまり、存在が現実的ではないのだ。伊江村を見ると、御崎はいつもガラスケースに入った宝石を思い浮かべた。確かに美しくて、ずっと見ていたいと思わせるが、扱いに気を遣うし、なくても困らない。実用的ではない。
御崎が入学当初から親しくしていた山上は、最初、
「美人はクラスに一人いればいいのよ! あたしの存在がかすむから、早いとこつぶしておかないと!」
などと真剣な顔で物騒なことを言っていたくせに、姉御肌なものだから、結局何やかやと伊江村の世話を焼いていた。
二人が親しくなったため、必然的に御崎にも伊江村と言葉を交わす場面が生じたが、正直なところ、御崎は彼女のことが苦手だった。「めんどくさい女だ」と思っていた。無口で何を考えているのかわからず、無用の緊張を強いられる。会話をするまでにいくつもハードルを越えなければならない。御崎はどちらかというと、山上みたいに屈託なく相手の懐に飛び込んでくるタイプのほうが好きだった。こんなふうに山上も浅井もいない状態で二人きりになると、本当に困るのだった。
「……」
「……」
雪に降られながら、歩道の真ん中で黙り込んでしまった。伊江村も困っているらしく、伏し目がちに右手で左手の手袋の先を引っ張っていた。
ここで「じゃあ」っていうのも不自然じゃねえ? もう十二時近いんだし、寮まで送ってくとか? でも寮につくまで何しゃべんの? 無言のままで御崎が焦ってぐるぐる考えていると、ふいに遠くからゴーンと鐘の音が聞こえてきた。
伊江村が不思議そうに顔を上げて、あたりを見回した。
「何の音だ」
「何って、除夜の鐘」
御崎が答えると、まばたきしながら伊江村が言った。
「初めて聞いた。テレビで見たことはあるけど」
「向こうの方に寺があるんだよ。いつもランニングの途中で通る」
東の方角を指さして御崎は言った。
「……見に行くか?」
伊江村がうなずいた。
雪の降り積もる歩道を、並んで歩いた。ゴーン、ゴーンと鐘は一定の間隔を空けながら鳴っている。街灯の明かりに照らされた部分だけ、ひっきりなしに降り続く雪が見える。
緊張して、息苦しかった。そのまま寮に送っていけば十分弱で済んだのに、なぜ遠回りを提案してしまったのかわからなかった。
「……雪が降ると、なんか静かだな」
静寂をごまかすべく御崎がそう言うと、伊江村が口を開いた。
「雪は氷の結晶が結合してできている。結晶の隙間が空気の振動を吸収するから音が伝わりにくくなる」
「……お前、モテないだろ」
味もそっけもない、無機質な答えに思わずそう言うと、伊江村が不思議そうに御崎の顔を見た。雪の話からモテるモテないの話に飛躍したのが理解できなかったのだろう。
「お前、なんで家に帰んないの。女子寮も合宿してんの?」
じっと見つめられているのに耐えられず話題を変えると、伊江村は淡々と答えた。
「帰る家がない」
「……」
地雷踏んだ、と焦った御崎に構わず、伊江村は続けた。
「中学生のときに母が死んで、父は最初からいないし、兄弟もいない。親類はいないも同然だから、一応、父の生家の使用人が名目上の保護者になっている」
「……悪かったよ」
隣から顔を見つめられて、居心地が悪かった。めんどくさい女じゃなくて、へんな女だ、と思った。
「うちも俺が中一のときに親父が死んでるんだけど、母親が再婚することになってさ」
しゃりしゃりと音を立てて溶けかけた雪を踏みながら、御崎は言った。
深刻な悩みというわけではなかった。だからよけいに女々しい気がして、誰にも話したことがなかったが、そのときは抵抗なく口から出た。彼女の自己開示に応えなければならない、と無意識に思ったのかもしれない。
七月のことだった。夏休みの帰省の予定をメールで伝えたら、会わせたい人がいる、と母が書いてきた。御崎も十七になっていたし、意味するところは想像がついた。
〈瑛子、再婚すんの?〉
すでに社会人になっていた三歳年上の姉に電話して探りを入れると、姉は開口一番に言った。
〈あんた、反対するんじゃないよ。お母さん、三人も子供抱えて大変だったんだからね〉
別に反対するつもりはなかった。
母の勤めている病院に入院していたという相手は、実際会ってみると、物腰も柔らかで誠実そうな人柄がうかがえた。自分は学費免除の情保学校に通っていたし、働き始めた姉が家に金を入れるようになったとは言っても、母が家計を支えるために働かなくてはならないことに変わりはなかった。母が穏やかに安心して暮らせるようになるなら、それが何よりだった。まだ小学生だった妹にとっても、男の保護者がいたほうがいいに違いない。
実際のところ、他人が家に入ることに対して、妹は微妙な抵抗感を抱いていたらしいが、義父の人柄は信用できると評価していた。きょうだい三人口を揃えて「母をお願いします」で話はついた。
「いい人だし、母親は必死に働かなくてもよくなったし、再婚してよかったと思ってんだよ。でも俺、もう十七だし、いまさら父親はいらないんだよな」
結婚を控えすでに独立の態勢に入っていた姉にとって、義父は「母親の再婚相手」でしかなく、小学生だった妹はいやおうなしに義理の親子関係を築かなければならなかった。家を出ているが学生だった御崎は、微妙な立場だった。
「それに、死んだ親父って、家長意識強い人だったんだよ。中学生の俺に『家にいる男はお前だけだからな。あとは頼む』とか言って死んでさ。病気なのも知らずに殴りあったりしてたから、罪滅ぼしのつもりもあって、ああ、俺が親父の代わりをしなきゃいけないんだって、そう思っちゃったんだよ。情保に入ろうと思ったのだって、学費払わなくていいし、公務員だし、学校出たらすぐ働けるからだしさ。いきなりもう父親役しなくていいよって言われても、どうしていいのかわかんねえよな」
言いながら、結局自分はファザコンで、本当は再婚する母を許せないだけなのかもしれないと思った。
黙って聞いていた伊江村が、口を開いた。
「いいじゃないか」
遠くを見たまま、伊江村は続けた。
「御崎はすぐに大人になるし、結婚して子どもも生まれて、父親になる。一度その覚悟ができたなら、御崎が望んだときに、必要とされたときに、すぐにそうなれる」
青白い街灯の明かりに照らされた横顔は、清らかで美しかった。
何か、託宣を聞かされたような気分だった。胸のうちがざわざわした。急に目の前の覆いを外されて、遠くにあるまぶしいものを見せられたような気がした。
それに、と言いよどみ、伊江村はひどく困った顔をして、もじもじしながら言った。
「御崎が家に帰らなかったから、わたしは今日初めて除夜の鐘をつきにいける。御崎は善行を積んだ」
「……何だそれ」
言いながら、頭の中で脳内物質がものすごい勢いで放出されたのがわかった。一気に、胸の内にあたたかくて甘い水を注ぎこまれたような気がした。
それは単純に、寄る辺なさと淋しさの共有から来たシンパシーだったのだろうが、たったそれだけのことで好きになってしまった。
伊江村がどう思ったのかは知らないが、少なくともこのとき以来、伊江村にとっての自分も「山上の友人」から「比較的親しい同級生」くらいにはなったようだった。十七歳らしい単純さで、御崎は距離を詰めようとした。
伊江村の母親が惨殺されていたのも、彼女が何か根深いトラブルを抱えているのも、知ったのはずいぶん後になってからのことだ。御崎に未来を見せたくせに、彼女自身は未来などちっとも見ていなかったのだ。