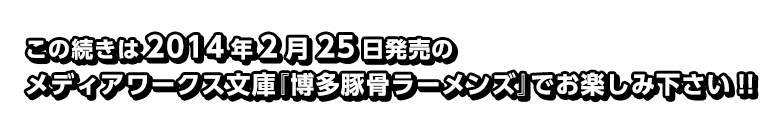1回裏
「……え? 転勤、ですか?」
突然の異動を言い渡されたのは、就職活動の際にあつらえた地味な色のスーツが、ようやく体に馴染んできた頃のことだった。デスクでふんぞり返っている七三分けの偉そうな上司の前で、斉藤は目を丸くした。
「そう、転勤。さっそく明日から」眼鏡の汚れを執拗に拭きながら、上司は無表情で頷く。「うち、人余ってるんですよ。人手が足りない支店に回してほしい、と言われまして」
なんとなく、予感はあった。
先日、斉藤は仕事で大きなミスをしたばかりだ。何らかの処罰を与えられるだろうと覚悟はしていた。でもまさか、それで転勤になろうとは。
「最近の新入社員は使えないと聞いていましたけど、まさかこれほどとはね」
「……申し訳ありません」
半年以上の研修を経て、ようやく任された仕事で下手を打った。それだけだ。入社一年目の新人に対する処罰としては、ちょっと厳しすぎるのではないだろうか。これでは、プロ初登板の試合で三回八失点と大炎上した大卒ルーキー投手に向かって、「君、全然使えないから他のチーム行ってくれる?」と無償トレードに出すようなものじゃないか。
もちろん、失敗した自分も悪い。斉藤だって、ひたすら謝った。上司にも、クライアントにも。土下座までして謝った。それでも、新入社員がミスしたくらいで左遷させるこの会社は、はっきり言って異常だ。だが、そんなことは前々から知っていた。この会社は、普通じゃないのだ。
「転勤先でも結果を残せなかったら、どうなるかわかってますよね?」
「はい」と返事をしたが、実際わからなかった。どうなるのか、想像もつかない。
「首を切られる覚悟くらいは、しておいてくださいね」
なるほど、左遷の次は解雇、無償トレードの次は戦力外通告というわけか。「……肝に銘じておきます」
「あなた、首を切るっていう意味、わかってます?」
馬鹿にしやがって、と思った。それくらい知っている。いくら三流大学の出身とはいえ、そんな慣用句を知らないほど常識がないわけじゃない。
「わかってます。解雇する、という意味ですよね」
「いいえ」そんなに甘い世界ではなかった。「文字通りですよ。刃物で首を切り落とす、という意味です」
ぞっとした。それがただの脅しでないことは、斉藤も十分わかっていた。現に先月、内部告発しようとしていた同期の新入社員が、突然、自殺体となって発見されたばかりだ。会社に逆らえば死が待っている。ブラック企業どころじゃない、ダーク企業だ。
「それで、私はどこに転勤なんでしょうか?」
「福岡支店です」
「えっ」思わず声が出た。「福岡ですか」
福岡といえば、あまりいい噂を聞かない。表向きは平和な観光都市で、食べ物もおいしく住みやすい町ではあるが、見えないところで犯罪が蔓延しているという。とくに福岡は、殺し屋産業の激戦区だった。戦場の最前線に送り出されるような気分だ。
「気をつけてくださいね。福岡には、コロシヤゴロシヤがいるそうですから」
「コロシヤゴロシヤ?」なにかの妖怪の名前だろうか、と斉藤は首をひねった。コロボックルとか、ケサランパサランみたいな。「なんですか、それ」
「『殺し屋殺し』屋ですよ。殺し屋殺し専門の殺し屋です。うちの社員も被害に遭っているそうですよ」
ますます気が進まなくなった。
殺人請負会社[マーダー・インク]。
斉藤の勤めている会社は、裏でそう呼ばれている。表向きは普通の人材派遣会社を装っているが、派遣しているのは殺し屋だ。昔、外国に実在した犯罪組織をモデルにつくられた会社だそうだ。
東京から博多へ向かう新幹線に揺られながら、斉藤は考えていた。どうしてこんな会社に勤めることになってしまったのだろうか。俺の人生はどこから間違ってしまったのだろうか。思えばあのとき、面接官にあの質問をされたときから、自分の人生はおかしな方向に進んでいる。
ようやく内定をもらった会社が、まさか殺人請負会社だったなんて。入社して半年、斉藤は一人前の殺し屋になるための研修を受けてきた。武器の使い方、尾行の仕方、鍵の開け方。体を鍛えるためのキャンプもあった。その途中、同期入社の新人は半数以上が脱落している。
あの面接のとき、「人殺しなんて悪いことはできません」と答えていたら、また違う結果になっていたのだろうか。なんて、今さらどうにもならないことを考えていると、だんだんと眠たくなってきた。電車の優しい揺れが、心地いい。
新幹線は、順調に福岡へと下っていった。
* * *
瞼が重い。ものすごく重い。眠いわけではない。つけまつげのせいだ。つけまつげが重たくて、気を抜けば目が半開きになりそうだった。「これであなたも目ヂカラ倍増!」とパッケージには記されていたが、これでは逆効果ではないか。倍増どころか半減だ。
女はよくこんなものをつけていられるな、と林憲明[リンシェンミン]は感心しながら、市営地下鉄の中洲川端駅で電車を降り、6番出口に向かっていた。通路にヒールの音が響く。足を動かす度に、胸まで伸びた真っ直ぐな黒髪が、規則的に揺れた。
標的の住所は聞いている。福岡市博多区須崎町一丁目。ハーツ東天神という名前のアパートだ。駅から歩いて十五分もかからないだろう。タクシーには乗らず、徒歩で向かうことにした。タクシーの運転手に顔を覚えられては困る。
地上に出てから、博多座の横の通りを直進した。ガラスの壁に、自分の姿が映り込んでいる。黒のワンピースに、ロングブーツ。化粧は普段より少し濃いめだが、どこからどう見ても女にしか見えない。よし、いける、と心の中で頷いた。
その先に片道二車線の昭和通りがあり、長い横断歩道を渡った。昭和通りを抜け、さらに奥へと進むと、最初のブロックの角に茶色いレンガ模様のアパートがあった。一階は煙草屋で、建物は七階建て。ハーツ東天神、と入り口に書かれている。
林はエレベーターで四階に向かった。いちばん奥の部屋に、標的がいる。四〇五号室。インターフォンを鳴らすと、ドアが少しだけ開いた。ドアチェーンはつけたままだ。隙間から、女が顔をのぞかせる。いかにも馬鹿な男にひっかかりそうな、馬鹿そうな女だった。寝ていたのだろう、ピンク色のもこもこしたルームウェアを着ていて、金に近い茶色の長い髪があちこち絡まっていた。化粧をしていないことを差し引いても、俺の方が美人だな、と思った。
「誰?」と女が林に尋ねた。
もし林が黒服で強面の男だったら、彼女はドアを開けなかっただろう。林が去るまで居留守を使っていたはずだ。だが、彼女はドアを開けた。訪ねてきた者が女に、それも自分と同じようなタイプに見えたからだ。
女の質問を無視して、林は訊き返した。「タカシ、いる?」
「だ、誰ですか、タカシって」女がとぼけた。男を匿っているからだ。「そんな人、知りません」
下手な演技だな、と笑いそうになる。女の言葉を無視し、林は部屋の中に向かって叫んだ。「ねえ、いるんでしょ? タカシ! 聞こえてるんでしょ! どういうことよ、説明しなさいよ! 誰なのこの女! あんた、二股かけてたわけ!?」
「ちょ、ちょっと待って」林の芝居に、女の顔色が変わった。「二股って、どういうこと?」
「あんたも知らなかったの? あの男ね、あたしとも付き合ってたのよ」
「うそでしょ、そんな」
嘘だ。「タカシはどこ?」
「今、シャワー浴びてるけど」
たしかに、女の背後でシャワーの音が聞こえる。
「あの男と別れ話をつけたいんだけど、中に入れてもらえる?」
女はこくこくと頷き、チェーンを外した。ドアを大きく開き、林を招き入れる。
にやつくのを抑えられなかった。
ふと、七匹の子ヤギの話を思い出した。あのときの狼の気持ちが、今ならよくわかる。自分を母親だと思い込み、簡単にドアを開けた子ヤギに対して、狼も拍子抜けしたことだろう。ちょろいな、と。
ハーツ東天神の間取りは最高だった。1LDK、玄関から入ってすぐにキッチンがあり、包丁が置いてあった。自分の得物を使うよりも、その場にあるものを使った方が足跡が残らなくていい。女が後ろを向いた瞬間、林は包丁に手を伸ばした。黒革の手袋をはめた手で、背後から女の口を塞ぎ、喉を掻き切った。
キッチンの反対側に風呂場があり、ちょうど男が出てきたところだった。女の喉から勢いよく血が吹き出す。シャワーを浴びたばかりの男は、今度は恋人の血しぶきを浴びた。水の滴る体と、腰に巻いた白いバスタオルが、真っ赤に染まる。いきなり目の前で恋人が死に、なにがなんだかわからず、男は茫然としていた。
「女を殺すのって、あんまり好きじゃないんだよな」キッチンの前で倒れている女から、風呂あがりの男へと、林の視線が移動する。「男を殺す方が手応えがあっていい。強い奴ならなおさらだ」
「お、お前」吹き出物だらけの若い男の顔が、恐怖を噛みしめるように、ゆっくりと歪んでいく。「誰だよ、何なんだよ」
「俺?」林は笑う。「殺し屋」
「まさか、華九会のやつか」ようやく状況を理解したようだ。「俺を殺すために、女に変装してきたのか」
「変装? 違うね。これはただの趣味。俺、好きなんだよ、女の格好するの。つけまつげは嫌いだけど」
男が部屋の奥へと逃げていく。血だまりを踏まないように気をつけながら、女の死体を跨ぎ、林も部屋の中へと進む。「お前さ、あのMirroir[ミロワール]ってクラブが、華九会の店だって知ってんだろ? そんな店から売上持ち逃げしようとしたら、痛い目みるのはわかってるよな?」
「わ、悪かった! 金なら返すから!」
「あー、いや。いらない。金はいいよ。別に取り返してこいとは言われてない。葬式代にでもすればいいさ。お前と」親指でキッチンを指す。「あっちで死んでる彼女の分。十分足りる額だろ?」
「た、助けてくれ」男は腰を抜かしていた。芋虫のように床を這い、林から逃れようとする。
「こういうことを赦しちゃうと、組の面子とかに関わるらしいんだよ。だから、華九会に逆らうやつはこうなるんだって、見せしめに、殺してこいってさ」
「借金があって、しょうがなかったんだ、もう二度としないから」
「ああ、借金ね。気持ちはわかるぜ。俺も借金あるから」
だからこんな仕事をしているんだけどな、と包丁をくるくる回しながら笑う。
「お前が盗んだ売上、一千万だって? いいよなあ。俺なんか、お前ら二人殺して、たったの百万しかもらえないんだぜ? 百万だよ、百万。お前らの命は、たったそれだけの価値しかないってことだ。切ないよなあ」
「だ、だったら、こうしようぜ」突然、男が声を弾ませた。「金は、残り四百万ある。お前に全部やるよ。それで見逃してくれ。な、金、ほしいんだろ?」
「馬鹿そうな顔しといて、そういうずるいことには頭が回るんだな。感心するぜ」
林は肩をすくめた。女に同情してしまう。この男、自分が生き残ることしか、頭にないみたいだぜ。お前が死んだことなんて、どうでもいいんだとよ。まあ、そんな男に引っかかる女も、自業自得だ。
「でもな、そういう問題じゃねえんだよ。一度引き受けた仕事はちゃんとやらねえとな」男の頭を掴み、耳元で囁く。「俺はプロの殺し屋だから」
そして、男の喉を一気に切り裂いた。
女を殺すのはあまり好きじゃないと言ったが、撤回しよう。部屋のクローゼットを物色しながら、林はそう思った。この女、なかなか服の趣味がいい。気に入った服をいくつかブランドバッグの中に詰め込み、ついでにそのバッグももらっておいた。女を殺せば服も手に入る。一石二鳥だ。
アパートを出て、昭和通りを天神方面に向かって歩いた。せっかく天神まで出てきたのだから、コアやパルコに寄ってウインドウショッピングを楽しんでおきたかった。新しい服を買うような金の余裕はないので、いつも試着をするだけだ。それでも、なにを着ても似合う自分を見ることが、林は好きだった。俺ってきれいだよね? この世でいちばん美人だよね? まるでどこぞの童話の女王様のように、鏡を見て悦に浸る。それと同時に、妹のことを思い出す。もう十年以上会っていないが、中国で暮らす妹も、今頃はこれくらい美しく成長しているんだろうな、といつも勝手に想像していた。女装して鏡を見ると、妹に会っているような気分になれるのだ。
身長百六十五センチの林が、ヒールのある靴を履いて街中を歩けば、それなりに目立つ。女にしては長身だ。人目を惹くのか、声をかけられることも多い。芸能事務所のスカウトやキャッチ、ナンパもされる。皆、林が男だとは気付かない。そんな馬鹿な男たちを、「馬鹿だな」と嗤うのが、楽しかった。
土曜日ということもあり、いつもより天神は賑やかだった。車も人通りも多い。何台もの選挙カーが走り回っている。もうすぐ選挙があるらしいが、林には関係のない話だった。林はまだ十九歳だし、日本国籍ももっていない。
選挙カーの中から手を振りながら、ウグイス嬢が「ありがとうございます」と何度も繰り返している。その甲高い声がひどく耳障りだったので、若者向けのアパレル店が集うビルの中に逃げ込んだ。そこでようやく、携帯電話が鳴っていることに気付いた。雇い主からの電話だった。着信画面に表示された『張[ジャン]』という文字に、嫌な気分になる。渋々、電話に出た。「なんだよ」
『どうして電話に出ないんだ』張の高く張り上げた声が、鼓膜をつつく。
「選挙カーがうるさくて、気づかなかったんだ」
『マナーモードにしておけ。ビジネスの基本だろうが、阿呆』
うるせえ。阿呆はお前だ。死ね。と、心の中で反抗する。「で、何か用?」
『仕事に決まってるだろ。俺がお前と世間話をするとでも思ったか?』
「残念。今日はもう閉店しました」
『殺し屋に閉店も開店もあるか』偉そうに、張が言う。『年中無休、二十四時間営業だ』
「殺人請負会社ってところは、週休二日制らしいぜ」
『それは嘘だろうよ。会社ってのは、都合のいい条件を提示するものだからな』
「俺は個人事業だ。休みたいときに休む」
ふん、と張が鼻を鳴らした。『借金がある奴は休むな。休む暇があったら働け。お前みたいな素人のガキを雇ってやってるんだから、少しは有難いと思うんだな』
素人じゃない、俺はプロだ。林はむっとした。
いつもなら「うるせえ。死ね。三回死ね」と悪態をつくところだが、今日は機嫌がいい。いい服も手に入ったし、借金地獄も、ようやく出口が見えてきた。あと五百万円払えば、張のもとから解放される。「まあ、いいや。我慢するわ。てめえのその脂ぎった顔も、もうすぐ見納めだからな。で、誰を殺ればいいんだ?」
『住所はメールで送る。武田という名前の、マル暴の刑事だ』
電話はそこで切れた。
刑事や暴力団員の殺しは、一般人より報酬が高い。相場では五、六百万といったところだろう。次の仕事が最後になりそうだ。足取りが、自然と軽くなる。
三越前の広場で、ミニスカートのコスチュームを着た若い女が、色とりどりの風船を子供に配っていた。家族向けのイベントが開かれているらしい。キャンペーンガールを横目に通り過ぎながら、林はなんとなく勝ち誇った気分になった。俺の方がスタイルもいいし、美人だ。そんなことを考えて、悦に浸る。気分がいい。
携帯電話を見れば、張からメールが届いていた。住所が書かれている。次の標的の住所は、箱崎だった。天神駅から福岡空港行きの電車に乗り、また逆戻りしなければならない。駅に着き、鞄の中から定期ケースを取り出した。中には、電子マネーの乗車カードと、一枚の写真が入っている。
電車に乗っている間、林はずっとその写真を眺めていた。古く、よれよれになったその写真には、若い女と小さな兄妹が写っている。母親と、林と、妹の僑梅[チャオメイ]だ。今から十年前、林が九歳のときに家を離れることになり、別れを惜しみながら撮影したものだ。父親は酒と賭博に溺れ、借金だけを残して蒸発した。貧しい林家は、子供を売らなければ生活できそうにもなかった。林はそれから殺し屋として働き、組織への借金の返済と、家族への仕送りを続けてきた。
林は心の中で、写真に向かって語りかけた。母さん、僑梅、もうすぐだよ。もうすぐ、すべて清算できる。やっと会いにいけるよ。
中洲川端駅から箱崎線に乗り換える。昔のことを考えていたら、あっという間に目的地についた。中洲川端駅から、四つあとの箱崎宮前駅で降りる。一番出口の階段を上がると、自転車置き場があり、その先に灰色の鳥居が見えた。鳩がたくさんいる。ざっと数えただけでも、二、三十羽といったところだ。
林は顔をしかめた。鳩は嫌いだ。鳩を見ると、いつも昔を思い出す。物乞いをしていた自分の姿を。町に出て観光客に群がる幼い頃の自分と、あの鳩たちが同じに見えた。地面をつついている鳩の姿が、道に捨てられた残飯をかき集める自分の姿と、重なる。
思わず首を振った。違う、あれは俺じゃない。俺じゃないんだ。ひたすら自分に言い聞かせる。俺は、あの頃の俺とは違う。強くなった。人を頼らなくても、こうやってひとりで生きていける。あの頃の小汚い姿とは、全然違うじゃないか。こんなに飾り立てて、きれいな格好で歩いているんだから。
筥崎宮を通り過ぎると、白と黄色が混ざったような冴えない色をした、十階建ての分譲マンションがある。ここが次の標的が住むマンションなのだが、なにやら様子がおかしい。マンションの前に人だかりができている。パトカーも数台停まっていた。立ち入り禁止の黄色いテープが張り巡らされていて、中には入れそうになかった。
いったいなにがあったのだろうか、と首を傾げていたところ、
「首吊りらしいわよ」
隣にいた主婦風の中年女が、訊いてもないのに教えてくれた。「首吊り自殺。さっき、このマンションの住人が話してるのを聞いたの」
「自殺? 誰が死んだって?」
「三〇九号の、武田っていう人だそうよ」
三〇九号室の武田。俺が殺すはずだった男じゃないか。自殺だって? なんだよ、それ。林は拍子抜けした。殺意がすっかり萎えてしまった。
* * *
警固公園の中央には、多くの人が集まっていた。マイクを片手に、現職の市長・原田正太郎が、支援者に向けて演説している。さすが元俳優なだけあって、喋りは上手い。集まった人間のほとんどがサクラだろうが、中には足を止め、携帯電話のカメラを向けている通行人もいた。
待ち合わせの時間の十分前だというのに、相手はもうすでに約束の場所で待っていた。馬場という名の、博多駅の近くで探偵事務所を構えている男だ。歳は重松より一回りくらい若いが、むしろ年上に見えるほど落ち着き払っている。顔の造りも悪くないし、手足が長くスタイルもいいのだが、どこか草臥れた雰囲気の男だった。猫背を直し、もう少しきちんとした格好をすれば女も放っておかないだろうに、彼は見た目に頓着しない。いつも髪はぼさぼさで、着ている服もだらしない。今日は、首回りのよれた白いカットソーに、古びたジーンズだった。勿体ない。宝の持ち腐れだと思う。
待ち合わせは警固公園の一角で、馬場は退屈しているのか、食べているパンを小さくちぎり、鳩に向かって投げていた。馬場の足元では、三羽の鳩が慌ただしく餌を取り合っている。馬場の近くを離れようとしない。すっかり懐いているようだ。馬場の髪の毛は癖が強く、鳥の巣みたいな頭をしているので、そのうち鳩が彼の頭の上で卵を産んでしまうかもしれない。そんなくだらないことを想像して、重松はひとりで笑った。
馬場が重松に気付き、片手を上げる。重松は、現金の詰まった大きなキャリーケースを引きずりながら、彼に近付いた。人ひとりが入ってしまいそうな大きさなので、運ぶのには苦労した。
「早かったな、馬場」
重松が近付いたせいで、鳩が逃げてしまった。馬場は少し寂しそうに笑う。「博多もんは、せっかちやけんね」
大学から福岡に住みはじめた重松とは違い、馬場は生まれも育ちも博多で、二十八年間ずっと福岡で過ごしてきた。訛りの強い喋り方をする。「重松さん、疲れた顔しとるばい。休む暇もないんやろ?」
馬場の言う通りだった。次から次に発生する犯罪のせいで、寝る暇すらない。
「餌があるところに鳩は寄ってくる。犯罪も同じだ」
今となっては、福岡市はよそ者の割合の方が多い。アジアの玄関とはよく言ったものだ。海外企業の誘致を積極的に進める市長の方針は、結果的に海外の裏組織まで歓迎することとなった。市内の暴力団だけでなく、アジア系のマフィアも参入し、この町の裏社会はますます活気付いている。
「この町も変わったねえ」と、馬場がしみじみと言う。「町も人も、みんな変わってしまった」
「変わらないのは、お前と『通りもん』くらいだよ」馬場の隣に腰を下ろし、重松は本題を切り出した。「今朝、うちの署の刑事が遺体で発見された」
馬場はたいして驚かなかった。「あらら」
「自宅で首を吊ってた。俺も世話になった先輩刑事だ」
「首吊り? 自殺なと?」
「遺書はあった。証拠品を横領したことがバレるのが怖くて、死ぬんだとよ」
「ばってん、そうとは限らん」馬場が横目でこちらを見た。「って、重松さんは思っとるっちゃろ?」
重松は頷く。「金と権力さえあれば事実が買えるからな、この町は」
殺し屋に金を払って殺させ、警察に金を払って口裏を合わせてもらえば、自殺なんて簡単に偽装できるだろう。
「あの人は、いつも真っ直ぐな人だった。嘘が下手くそでな。たまにフォークを投げようとしても、全然落ちなくて結局ストレートになるんだ。少なくとも、証拠品を横領するような人じゃない」
「なるほどね」
「これを見てくれ」重松は、背広の内ポケットから、一枚の写真を取り出した。「鑑識に十万払って手に入れた、現場写真だ」
自殺した刑事の首元が大きく写っている。太い縄の痕が、首を一周するように刻まれていた。
「縄の痕以外に、斑点のような痣がいくつかあるだろ? これは自殺じゃない。扼殺だ。気管支と、動脈と静脈、人間の急所をピンポイントで指圧している」
「プロの仕業やろうね」
「ああ」
重松は、今度は封筒を取り出した。写真と同じくらいのサイズの、白い封筒だ。
「昨日、俺の家にこんな封筒が届いた。匿名だが、送り主はあの人しかおらんやろう。中には、写真が一枚入ってた。いかにもヤバそうな写真だ」
「自分が消されることを、うすうすわかっとったわけか、その先輩は」
「なあ、馬場」封筒を馬場に向かって差し出す。「この仕事、引き受けてくれるか?」
人がひとり死んでいる案件だ。もっと渋られるかと思ったが、馬場は意外にもあっさりと承諾した。「よかよ」
「助かるよ。これ以上、悪党を野放しにしてはおけん。すぐ使えるように、金は現金で用意してる。足りなければまた言ってくれ」
キャリーケースも渡す。馬場は少しだけ開けて、中身を覗きこんだ。札束が大量に詰まっていることを確認してから、封筒を開ける。
中の写真を見て、馬場は珍しく目を丸くした。写真に写っている男と、今ちょうど公園の中央で演説している男を見比べてから、声を潜めて言う。「これ、原田市長やんか」
その写真は、どこかの高級クラブで盗撮されたようなものだった。おそらく店のボーイを買収して撮らせたのだろう。写真の中央で、福岡市長の原田正太郎が、スキンヘッドの男と話をしている。相手は後ろ姿しか写っていないので、誰かはわからない。市長の隣には女が、奥の方には店のボーイが写り込んでいた。この写真をもっていた刑事が殺されたということは、それなりに意味のある場面なのだろう。
「つまりその先輩は、市長の悪事を暴こうとしたばってん、殺されてしまった。その無念を俺たちが代わって晴らしちゃろう、ってわけね」
「そういうことだ」
原田市長には、裏では黒い噂が絶えなかった。元俳優で、地方政治に何の関係もなかった彼が市長選に当選したのは、ネームバリューのおかげだけではない。福岡の裏組織との癒着があってこそだ。ひとりの人間に、あまりに権力が集中しすぎている。これ以上、市長の好きにさせておくわけにはいかなかった。
「悪いな、馬場。いつもお前にばっかり、汚れ仕事をさせて」
「気にしなさんな。そういう重松さんだって、この金用意するのに結構汚れたんやない?」
「犯罪者と戦うには、犯罪者になるしかないからな」
馬場は、写真に写り込んでいる女を睨みつけている。「誰やろうね、このべっぴんさん。キャバ嬢には見えんけど」
「さあ、市長の秘書じゃないか?」重松は、公園の中央を指差した。「ほら、あそこにおる、あの女」
原田市長が演説を終え、支援者たちに近付き、握手を交わしている。その斜め後ろに、若い女がいる。なんとなく、写真の女に似ているような気がした。
「ちょっと行ってくる」
馬場が動いた。立ち上がり、真っすぐに歩いていく。
「おい、どこ行くんだ」
呼びかけるが、返事はない。
馬場の視線の先には、子供がいた。幼稚園くらいの男の子だ。保護者らしき人物は近くにいない。その子供は、大きな木を見上げていた。視線の先には風船があった。どうやら、風船の紐を手放してしまい、木にひっかかってしまったらしい。
「坊主」馬場が子供に声をかけた。「待っときい、お兄ちゃんが取っちゃるけん」
馬場は、少し離れた場所から助走をつけ、飛んだ。長身なので、右手をのばすと簡単に紐に手が届く。
半泣きだった子供が「おいちゃん、ありがとう」と喜んだ。ほほえましい光景だなと、重松の頬も自然と緩む。
ところが、次の瞬間、予想もしないことが起こった。
その風船を、馬場は勢いよく踏みつけたのだ。煙草の火を地面でもみ消すかのように、靴の踵でぐりぐりと押し潰した。
これには重松も驚いた。
風船は、割れた。乾いた破裂音があたりに響き渡り、その場がしんと静まり返った。一拍置いてから、子供は泣き出した。そりゃ泣くだろうな、と重松も思った。我が子を見つけた両親が、向こうから慌てて走ってくるのが見える。まずい。
「あー、そげん泣かんと。もっといいもんばあげるけん」面倒くさそうに馬場が言う。財布から一万円札を取り出し、子供にこっそり手渡しながら、耳打ちした。「これでお菓子でも買いんしゃい」
おもしろいくらいぴたりと泣き止んだ子供に、重松は何ともいえない気分になってしまった。たしかに一万円あれば、風船などいくらでも買えるだろうが、可愛げがない。
一方、馬場は楽しそうに笑っている。「現金なガキやね。裏の仕事に向いとるよ」
それにしても、この馬場という男は、相変わらずなにを考えているのかわからない。どうして風船を割るという奇行に走ったのか、重松はその説明を求めた。「いったいなにがしたいんだ、お前は。おじさん呼ばわりされたのが、そんなに気に入らなかったのか?」
「風船が鳴った瞬間の、あの女の行動を見とったと」
「女の行動?」
「銃声が鳴ったら、あの女はどげん反応するかなって思って、試しに風船を割ってみた」
言われてみれば、あの風船が割れた音は、発砲音のように聞こえなくもなかった。最近、福岡では暴力団の抗争が激化しており、発砲事件も増えている。突然、大きな音が鳴れば、銃声かと身構えるのは当然だろう。命を狙われる立場にある市長とその周囲の人間ならば、なおさらだ。
「驚いたら、ただの秘書。驚いて市長の背中に隠れたら、愛人。市長の盾になろうとしたら、ボディガード」
「それで、結果は?」
「胸元に手を伸ばして、周りをきょろきょろ見渡しとった。ありゃ、殺し屋の仕草やね」
「なるほど、市長が雇った殺し屋か。だが、先輩を殺したのは、あの女の仕業じゃないだろうな」
「やね」
写真の女は、爪が長く、きれいに手入れをされていた。彼女がこんな殺し方をすれば、被害者の首にもっと爪痕が残っていることだろう。
「他にも殺し屋を雇っとるかもしれん。榎田に調べてもらおっか」と、馬場が提案した。榎田というのは、馴染みの情報屋の男だ。昔、外国のハッカー集団に所属していたこともあるらしく、手に入れられない情報はないとまで言われている天才だ。
「そうだな。あいつの守備範囲なら、なんとかなりそうだ」
「なにかわかったら、また連絡するけん」
と言い残して、馬場はキャリーケースを引きずりながら、警固公園をあとにした。
* * *
しばらく眠っていたようだ。斉藤が目を覚ましたときには、新幹線はもう広島まで来ていた。窓の外に球場が見える。試合開始までまだ時間はあるが、すでに客がたくさん入っているようだった。そういえば、今は十一月初め。プロ野球は日本シリーズの季節だ。今年のカードはカープ対ホークスらしい。なかなか珍しい組み合わせで面白そうだとは思ったが、観ようとは思わなかった。
球場を眺めていると、昔の記憶がよみがえってきた。高校のときの、甲子園の予選の試合。マウンドに立つ自分の姿。3回裏ツーアウト、打順は9番、ピッチャーだった。斉藤は渾身のストレートを投げようとした。ところが、球はすっぽ抜け、打者の頭に直撃した。相手打者は弾かれるように一回転して倒れ、そのまま蹲った。チームメイトや、相手の監督が呼びかけても、ぴくりとも動かなかった。担架に乗せられ、運ばれていった。その間も打者はまったく動かず、まるで死体を運んでいるかのように見えた。
まだ3回だというのに、斉藤は滝のような汗をかいていた。頭の中は真っ白で、ただ茫然と立ち竦んでいた。ロージンまみれの右手が震えた。
プロ野球ならば、危険球で一発退場になるところだろう。高校生の斉藤は、その後の登板を許された。ところが、気持ちを切り替えることはできなかった。死球の動揺が、斉藤のピッチングを崩していく。制球が乱れ、ストライクが入らない。また当ててしまうのではないかと思い、ボールが打者から離れていく。自然と、勝負を避けてしまっていた。三者連続フォアボールで、塁に走者を溜めたまま、斉藤はマウンドを降りた。
元々、エースの斉藤ひとりでもっているようなチームだったので、斉藤が降板してからは散々だった。二番手ピッチャーは、走者一掃のタイムリースリーベースを打たれ、あっという間に3点を取られた。相手の勢いは止まらず、気付けばこの回だけで7点も離されてしまっていた。斉藤は、相手ナインのバットの快音を聞きながら、ベンチで頭を抱えることしかできなかった。
『最後まで諦めるな』と監督が言った。それは彼の口癖だった。監督は項垂れる斉藤の隣に座り、呪文のように何度も唱えていた。『最後まで、なにが起こるかわからない』
だが、7点の点差を追いつくことなんて、到底無理だということはわかりきっていた。斉藤のチームは、エースの斉藤が抑え、少ない点差を守り勝つ、守備に重点を置いたチームだった。大きな点差をひっくり返すような打撃力はない。7点差からの大逆転なんて、そんな奇跡みたいなことが、そう簡単に起こるはずがない。斉藤は唇を噛み締めた。
『最後まで諦めるな』と言う監督の目は、虚ろだった。斉藤には、彼がいちばん諦めているように見えた。
結局、チームは負けた。試合が終わってから、斉藤は監督に連れられ、死球を当てた相手の見舞いに行った。意識は回復したが、しばらくはリハビリが必要だと、医者が言っていた。春も夏も、大会には出れないだろう、と。自分の一球が、相手の青春を奪ったのだ。何度見舞いに行っても、顔も見たくないと袖にふられた。
それだけではない。斉藤自身にも、問題が生じた。体の異変に気付いたのは、大会後の最初の練習のときだった。特にインコースに投げようとすると、必ず暴投になる。あのときの恐怖がフラッシュバックし、人に向かって投げるのが怖くなった。やがて、キャッチボールでさえもコントロールが利かなくなってしまった。
思えばあのとき、頭部死球を当てたあのときから、自分の人生は狂っていったのかもしれない。あの一球さえなければ、甲子園に出場し、スカウトの目にも留まり、プロの世界に入っていたかもしれない。あの一球で、人生がだめになったのだ。
いやなことを思い出してしまった、と斉藤はため息をついた。意識を野球から逸らそうと、車窓から横の席へと視線を移す。隣の席に座っているサラリーマン風の男は、新聞を読んでいるところだった。西日本だけのローカル紙だ。退屈だったので、横目で新聞を盗み見た。物騒な文字が目に飛び込んでくる。暴力団の抗争、発砲事件、外国人暴行殺人、婦女強姦殺人、野良猫の虐殺事件。すべて福岡で発生している事件の記事だった。いったい何なんだ、福岡という町は。不安が募った。