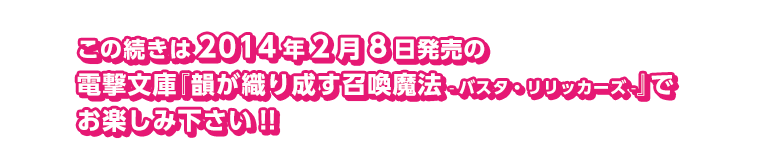第二話 イメージダウン・ブレイクダウン
生徒会室のある高等部の第一校舎から、渡り廊下を使って第四校舎まで行く。第四校舎から裏手に回ると、昨日マミラダに担がれて屋根を走った第一体育館がある。
そこから左にまっすぐ行けば、テニスコートが併設された第二グラウンドがあり、そのさらに奥が学院の隅っこ、悪名高い三号棟のある場所だ。真一は現在、そこを目指して第一体育館の脇を歩いていた。
あのあと真一は生徒会室に戻り「誰もヒップホップ研究部に立ち退きを了承させられないのなら、俺が直々に三号棟まで行って説得してきてやる」と告げた。これまで自ら動こうとはしなかった真一の変貌ぶりに、役員一同は怪訝に思ったようだが、シスター森崎だけは「ついに会長自らが粛清を下しに行くのですか! 作戦名は『無限大の正義(インフィニット・ジャスティス)』ですねっ! 神はあなたの味方です!」と拍手喝采の賞賛を送ってきた。
今まで三号棟に行くのを拒み続けていた真一が、どうして突然手のひらを返したようなことを言い出したのか。それはもちろん、サタニックマイクの力をあてにしてのことだった。
「なかなか悪知恵が働くね。やっぱり真一は魔王の素質ありだよ」
マミラダが真一の周囲をくるくると飛び跳ねながら言った。
「これは悪知恵ではない。俺のイメージダウンは悪魔のお前のせいなんだ。だから多少は悪魔の力を使ってイメージの回復を計っても、バチは当たらないだろう」
そう、三号棟に巣食う不良どもを一掃するためなら、なんでもしてやる。たとえ恥ずかしいラップを熱唱することになったとしても。真一は本気だった。
「とりあえず、そのヒップホップ研究部を支配するところから始めるんだね! やるぅ!」
「支配ってわけじゃないが……とりあえず、サタニックマイクを使って奴らに三号棟から出て行ってもらう。そしてクラブを解散してもらう」
悪名高いヒップホップ研究部は、今まで誰が何を言っても、断固として退去しようとはしなかった。そこで自分が出向いた途端、あっさりと立ち退きを了承させたとすれば、全校生徒から厚い信頼を取り戻せるに違いない、と考えたのだ。
真一は自分が生徒会長に再選したあとのことを妄想する。
「よっ、さすがは生徒会長!」「もう会長は音川くんしかいないわ!」
そんな声が聞こえるなか、鏡波学院のメインストリートで「再選おめでとうパレード」が開かれるのだ。先頭は吹奏楽部で、奏でる音楽はヴェルディ作曲の『凱旋行進曲』がいい。
そして俺はラグビー部が引く神輿に乗って、沿道で校章入りの旗を振っている生徒たちに手を振りながら微笑みかけるのだ。沿道の生徒たちが持つ垂れ幕には、鏡波学院の歴史上、もっとも偉大な生徒会長を称える言葉として「トップ・オブ・ザ・ヒーロー」の文字が……。
「ねえ真一。さっきからどうして、気持ち悪い顔をしているの?」
マミラダの声で我に返った。つい、にやにやと薄ら笑いを浮かべていた。
真一は羞恥心を隠すためにも、咳払いをして颯爽と歩を進めた。
「それにしても、あれだねー」マミラダが少し気恥かしそうに言った。「真一が私の結婚相手になるかもって考えると、一緒にいるのもなんだか、なんだか照れますなー」
「だから俺は悪魔と結婚するつもりは……」そこで真一は気づいた。女悪魔の姿がばっちり見えていることに。「お、お前、なんでそのままいるんだ! 早く姿を消せって!」
「えー、だから姿を消してると疲れるんだってば。周りには誰もいないんだし、いいじゃん」
マミラダがむくれながら言った。確かに第一体育館の脇道は、放課後になると人通りもほとんどなくなるのだが、誰かに見られる可能性はゼロではない。
「その油断がヤバイんだって! そもそも、許可なく部外者を学院内に連れ込むことは禁止されているんだ。今は選挙前の大事な時期だし、部外者と一緒にいるところを見られたら……」
「私が学院の制服じゃなくて、悪魔の格好をしてるから不安なんだね? 大丈夫だよ、どうせ女子生徒のコスプレだと思われるだけだって」
「コスプレって言い張っても、マミラダが部外者だってことはすぐにバレる。マミラダみたいに容姿のいい女子が生徒にいれば、今まで目立たなかったほうがおかしいからな」
「え? えっと、それって……どういうこと?」
「この学院にあんなかわいい子いたっけ、何年何組だろってなるに決まっている。それで探されたら、俺が勝手に部外者を連れ込んだことがバレて……ん、どうした?」
マミラダは頬を真っ赤に染めて、うつむいていた。
どうやら「かわいい」と言われたことに照れているらしい。抱きついたり、キスをしたりしてくるくせに、容姿を褒められることには免疫がないようだ。
マミラダは恥ずかしそうに顔を背けたまま、景色に溶け込むようにゆっくりと姿を消した。
「……よくわからん奴だな」
透明化したマミラダは、三号棟に到着するまでひと言も話さなかった。
◇
近くで見る三号棟は、まさに不良のたまり場という印象だった。
コンクリートの壁には、いたるところにスプレーで描いたグラフィティアートが施されている。「アート」とは言っても、別段、芸術性は感じられない。太陽やひまわりといった小学生が描くような稚拙な絵ばかりだった。
それから目立つのは黒や赤のスプレーで書いた「我らバスタ・リリッカーズ」「クレイジーホース最高」といった文字だ。滑稽なのは「FACK YOU」という落書き。スペルが間違っている。それを見ただけで、ヒップホップ研究部の知能をうかがい知ることができた。
一階にある三つのドアはすべて表に面している。二階へ続く階段も表にあり、壁伝いに鉄柵の取りつけられた廊下が伸びている。二階にもドアが三つあった。
ヒップホップ研究部の部室は、一階中央の部屋。そこのドアにも、やはりスプレーの落書きと、毒々しいステッカーが無数に貼られていた。
真一は深呼吸をしたあと、思い切ってヒップホップ研究部のドアをノックした。
返事はない。ドアに耳を押し当ててみたが物音も聞こえない。躊躇しつつもドアノブを回してみたが、鍵がかかっていた。
どうやら留守らしい。せっかく気合いを入れてきたのに、とんだ肩透かしをくらった。
……仕方ない。ここは後回しにして、先にオカルト研究部の様子を覗いてみるか。
ヒップホップ研究部以外で唯一、三号棟に入居しているオカルト研究部は、すでに立ち退きを了承済みだ。それでもせっかく来たのだから、念のために再確認したほうがいい。
二階へ続く階段をゆっくりと登る。三号棟の築年数はかなり古いらしく、鉄の階段もサビだらけだ。一段登るたびに、ギチギチと耳障りな音が鳴る。真一が提案するまでもなく、老築化が原因で解体されるのも時間の問題だったかもしれない。
二階の壁にもヒップホップ研究部の落書きがたくさんあった。こんなところに部室をあてがわれても、すぐに逃げ出したくなる気持ちがわかる。三号棟は全体的に無法地帯だった。
ただ、オカルト研究部の部室がある二階の左端には、一切落書きがなかった。その代わり、入り口のドアには怪しげな魔法陣が小さく描かれている。これはおそらく、オカルト研究部が自ら描いたものだろう。
その魔法陣は真一が昨日、三年八組の教室で見たものと似通っていた。
そこでふと思い立つ。あの魔法陣を描いたのも、ここの人間ではないだろうかと。今まで考えなかったのが不思議なくらいだ。
……ひょっとして、ここの連中も無法者なのか?
なんだか嫌な予感がする。真一は先ほど同様、恐る恐るドアをノックしてみた。
反応がない。こっちも留守なのか。そう思ってドアノブをひねると、あっさり回った。
「こ、こんにちわー、生徒会長の音川真一ですが……入るぞー?」
若干の緊張を覚えながらも、オカルト研究部の部室内に足を踏み入れる。
そこは真っ暗な部屋だった。三号棟の外から見た限り、各部室には日光を取り込む南向きの窓が取りつけられているはず。それなのに、光が一切入ってきていない。
それもそのはず。教室の半分ほどの広さの部室内は、四方の壁が天上まで届く巨大な書架で覆い尽くされていたからだ。それで窓すらも塞いでしまっている。どうりで、むあっとする息苦しい湿気を感じるわけだ。
とりあえず、ドアの傍にあった照明のスイッチを押す。天井の蛍光灯が、しばらく明滅したのちに点灯した。
蛍光灯の明かりで浮かび上がったオカルト研究部の部室内は、異様な雰囲気だった。
床には、昨日の三年八組で見たものと同様の魔法陣が描かれている。ただしこちらは、広さの都合上、やや小さいものだった。奥には生徒机を寄せ集めて作ったテーブルがあり、そこに火の灯されていないロウソクや、頭蓋骨の置物、銀枠の卓上鏡、そしてアルコールランプや、フラスコといった実験器具などが、秩序なく置かれていた。
「なんだか落ち着く雰囲気ですなー」姿を消していたマミラダが突如現れた。「ここは私好みの部屋だよ、うんうん」
マミラダは興味深そうにあたりに視線を投げながら、部室内を歩き回る。
「だから姿を見せるなってば」
「別に誰もいないんだから、いいじゃん……って、うわあ!?」
振り返ったマミラダが小さく悲鳴をあげた。その目は真一の右隣に向けられている。
真一がそちらに顔を向けると、
「うわあああッ!?」
同様に悲鳴をあげた。ドアの影に、三角座りでうずくまっている女子生徒がいたからだ。
その女子生徒の漆黒の髪はとても長い。左目が完全に覆われてしまっているため、右目だけで、傍に立つ真一をじっと見上げている。非常に不気味だ。最初からそこにいたようだが、どうして今まで何も言わなかったのかも不気味だ。
女子生徒は別段驚く素振りもなく、三角座りのままポツリと口を開いた。
「……今、そっちの人が突然現れた。それにその姿……悪魔?」
「はは、な、何を言ってるんだキミは。俺は生徒会長の音川真一だぞ」左腕の腕章を見せながら言った。「この俺が悪魔なんかと一緒にいるわけがないだろ。彼女はそうじゃなくて……」
「はいはーい、悪魔でーす!」マミラダが元気に挙手した。
「ば、バカ、お前、何を言って……!」
狼狽する真一を尻目に、女子生徒は「やっぱり」と立ち上ってマミラダに近づいた。
「け、今朝……三年八組の教室がおかしなことになっていたけど……あ、あなた様が降臨されたから、だったのですね……?」
女子生徒は、ほの暗さを感じさせるトーンで、ゆっくり、そしてオドオドと言葉を紡いだ。
そうだよ、とマミラダが答えると、女子生徒は仰々しくその場に跪いた。
「わ、私は三年八組の……よ、夜原麻里子と申します。あ、浅ましくも昨日、あなた様を召喚しようとした人間でございます……」
「なにぃ!?」真っ先に反応したのは真一だった。「やっぱりあの魔法陣を描いたのは、オカルト研究部だったのか! あんたのせいで、俺がどれだけ大変な……」
言葉が止まってしまったのは、夜原が形容し難いすさまじい形相で睨んできたからだ。髪がかかっていない右目だけで睨まれたものだから、その迫力は絶大だった。
「……せ、生徒会長のあなたが、ど、どうして、悪魔様と一緒にいるのかしら……?」
「真一が私の契約者だからだよ」答えたのはマミラダだった。「私を召喚したのも真一だし」
「なんですってぇぇッ!?」
今度驚いたのは夜原だ。まるで歌舞伎役者のような大げさなポーズで飛び退いている。それまで暗く静かな口調だったのに、その気になればハキハキと喋れるのかもしれない。
こほんと咳払いをした夜原は、またしても暗い調子で、オドオドと話し始めた。
聞くところによると、どうやら夜原は、この部室よりも広い自分の教室で悪魔召喚の儀式を行なおうとしていたらしい。室内を暗くして魔法陣を描き、ロウソクを灯す。あとは呪文を唱えれば悪魔が召喚できるかと思いきや、何も起こらなかった。手順が違うのかもしれないと思い立ち、この部室に戻って書架に並ぶ数々の魔導書を調べあさった。
調べているうちに、斜陽を魔法陣に当てればいいと知った夜原は、急いで教室へ戻った。そのときにはすでに、教師たちによって教室が閉鎖されていたそうだ。ちなみに三年八組の教室は今も使用不可となっており、今日の授業は別の教室で行なわれたらしい。
「なるほど……確かに俺は窓に貼られていた画用紙を剥がしたな。それで西陽が差し込んできて儀式が完成、マミラダが召喚されたってわけか」
そのおかげで迷惑をこうむった、という言葉を真一は飲み込んだ。それは夜原の前で言わないほうがよさそうだと判断したからだ。
「そっかー。じゃあ真一は最後の仕上げをしただけだったんだ。魔術の知識もなさそうな真一が私を召喚するなんて、変だと思ったんだ」マミラダも納得したらしい。「それにしても、私を召喚する魔法陣を用意できるなんて、麻里子ってすごいんだね」
「べ、別にたいしたことじゃありません……」
マミラダに褒められた夜原は、ぷいっとクールに顔を背けた。その顔は、机にある卓上鏡に反射して写っている。ものすごく笑っていた。ものすごく嬉しそうだった。
「もしかしたら私の契約者になるかもしれなかった麻里子に、挨拶しとかないとね。私はマミラダ。マミラダ・リファソラ・メフィストフェレス。大悪魔メフィストフェレスの娘だよ」
その名前を聞いた夜原は、目を丸くした。
「あ、あの、めめ、メフィストフェレス様……? そ、そんな方が召喚されたなんて……」
どうやら自分でも何が召喚できるのか、わかっていなかったらしい。
「そうだよ。私を召喚できた人間は四人目なんだから。レアだよー? やったね麻里子!」
「で、でもこの男が……メフィストフェレス様の契約者……」
真一は再び夜原に睨まれた。右目だけで。改めて見ると、夜原の髪は本当に長い。腰より下まで伸びていた。きちんと切りそろえていないのか、長さもバラバラだった。
「麻里子は魔術に造詣が深いんだねー。うわあ、中世に書かれたグリモワールの写本まであるじゃん。こんなの、どこで手に入れたんだよ。よーよー」
マミラダは興味深そうに部室内の書架を眺めている。真一は別に興味があるわけではなかったが、未だに睨みつけてくる夜原の視線から逃げるためにも、マミラダとは反対側の書架に目を向けた。
そこに並ぶ本の背表紙をざっと見渡す。魔術書の類いだけでなく、ヘーゲルやデカルトといった哲学書も並んでいた。日本語以外で書かれたタイトルも多い。
「これは英語、じゃないな。ラテン語かな。こんなもの読める……のかッ!?」
真一は口から心臓が飛び出しそうになった。書架の背表紙を眺めていたら突然、黒魔術の儀式に使用するような意匠のナイフが飛んできたからだ。そのナイフは真一の頬をわずかにかすめて、書架に並ぶ分厚い本の背表紙に「カッ」と刺さっていた。
こめかみに流れる冷たい汗も拭わずに、ゆっくりと振り向く。マミラダと夜原は何事もなかったかのように、ちょうど反対側の書架を眺めていた。
「あー、ゲーテの『ファウスト』もある。私のパパが出てくる小説だね」
「そ、それは私の愛読書でございます……わ、私は昔から、メフィストフェレス様の大ファンでございまして……」
二人とも普通に会話をしている。真一のすぐ傍にナイフが飛んできたことなど、気づいていない様子だった。
訝しく思った真一はもう一度、二人に背を向ける形で書架に向き直った。
そしてすぐさま振り返る。
夜原が二本目のナイフを振りかぶったところだった。
「や、やっぱりあんたか! 今俺を殺そうとしただろ!」
「ち、違う……」夜原は今にも泣き出しそうな顔で、首をふるふると左右に振った。
「違うとか言いながら、その手に持っているナイフはなんだ!?」
「り、リンゴでも剥こうかと……」
どこにリンゴがあるんだ。幼稚園児だってもう少しマシな嘘をつくだろう。
「んー? どうしたの?」マミラダがのんびりと尋ねてきた。そして夜原が背に隠したナイフを見るなり、あはは、と笑った。「麻里子って面白いね。そっか、真一を殺したいんだ」
「そ、そんな、メフィストフェレス様の契約者を、こ、殺そうなんて滅相もない……」
「遠慮しなくてもいいって。私のことは気にしないで、いつでも真一を狙っていいよ。魔王たるもの、いつでも寝首をかかれる覚悟をしておかないとね」
あまりにもバカなことを言い放ったマミラダは、それっきりこちらに興味を示さず、書架の本を手に取ってパラパラと読み始めた。コンビニで立ち読みをしている人は、周囲の買い物客が何を買おうと関知しない。振り向くこともない。それと同じだった。
殺人の許可を得た夜原は、ナイフを握ったまま真一を見てニヤリと微笑む。彼女のもつ暗い雰囲気も合わさってか、それは病的な笑顔に見えた。
「お、音川くんを殺したら、メ、メフィストフェレス様は私のもの? ぐふふふ……ふッ!」
不気味な笑い声の最後に乗せた裂帛の息とともに、夜原は再びナイフを投げてきた。それはとてつもなく機敏な動きだった。
「やめろおおおおお!」真一はすかさず横に転がってナイフをかわす。さっきまで立っていた場所に、ナイフがドスッと刺さった。
こめかみを流れる冷たい汗が床で跳ねる。夜原から漂う殺気は本物だった。真一を殺せば、マミラダを独占できると思っているらしい。とんでもない変態女だ。目の輝きも狂気じみており、完全に「イッて」しまっている。
「わ、私とメフィストフェレス様のために……し、死んでくれるかしら、音川くん……」
夜原がスカートの裾をゆっくりと捲った。これまた病的に青白い太ももには、数本のナイフが収められたホルスターが巻かれていた。そこから新たなナイフを一本抜き出す。
「ほら真一、そのままじゃ殺されちゃうよ?」
マミラダは振り向きもせず、本に目を落としたままのんびりと言った。コンビニで立ち読みをしている人が、背後の陳列棚の商品を選んでいる友人に語りかけるかのように。
「わかってるなら、なんとかしてくれ!」
「自分でなんとかできるはずだけどなー。真一にはそれだけの力があるんだしー」
……そうだった。俺はその力でヒップホップ研究部を屈服させるために、三号棟へ来たんだった。ようやく思い至った真一は、今にもナイフを投げてきそうな夜原を見据えたまま、例の恥ずかしい呪文を唱えた。
「のの、ノイズを取る、このマイクバトル!」
真一の右手が一瞬だけ白く輝く。直後に出現したサタニックマイクを握りしめて構えると、ドクロの装飾品を夜原に向けた。ドクロの両目が赤く光る。
夜原がそれを見ると同時に、どこからともなく、単一のフレーズで構成されたバックトラックが流れ出した。
「こ、これは……?」
夜原の動きが制止した。サタニックマイクのドクロの装飾品を見てしまった以上、もうほかの行動を取ることはできない。強制的にラップバトルに引きずり込まれるのだ。
「これがマミラダと契約して俺が得た……悪魔の力、らしい。ごめんな、こんなアホな力で」
「おいそこ。なんで謝る?」
マミラダの冷ややかなツッコミは無視して、真一は「行くぞ!」と自分に言い聞かせた後、さっそくリリックを紡ぎ出した。
【いきなりナイフを投げんな、変態女。テメェはマミラダにとっても圏外女。俺は我慢の限界なんだ。テメェに一つ言っておく。この俺が一発斬っておく。召喚ミスはテメェのせい、鈍感メスが責めんじゃねぇ。ナイフじゃなくてマイクで来い。オカルト研究上等だ、デカルト全球暴投だ。グリモワールもデッドボール】
真一の放ったリリックは立体的な黒い文字として出現し、部室内を縦横無尽に飛び交った。それらが一箇所に集まっていくと、野球のユニフォームを着た哲学者、ルネ・デカルトに姿を変えた。当たり前だが幻影だ。本当にこの力は、あまりにもバカバカしい。
なんなのよこれ……と驚いている夜原に、召喚されたデカルトの幻影は大きく振りかぶって白球を投げた。それは大暴投して夜原の顔面に直撃する。デッドボール。
「きゃあっ!」
意外と女の子らしく、かわいい悲鳴をあげる夜原。デカルトは「我思う、ゆえに我あり」とつぶやきつつ、さらに暴投を続けて次々とデッドボールを浴びせた。本当にバカバカしい。真一は心の中で謝罪する。デカルト先生、ごめんなさい。
デカルトの投げる白球も幻影なので、夜原の体に直接的なダメージはない。魔力の込められた言葉の弾丸は、精神面に強いダメージを与えるのだ。
夜原は片手をかざして白球の幻影から顔を守りながら、マイク代わりにしたもう片方の手を口元に近づける。そして真一に負けじとリリックを放ってきた。
【め、メフィストフェレス様は私のもの。横取りした貴様は、ただの邪魔者。魔術を知らない半端モンのガキ、見せてやるわソロモンの鍵。バフォメットも言ってる『アホめっ』と。サバトの儀式でぶっ殺す。魔法の餌食でぶっ殺す】
さすがはオカルト研究部というべきか、夜原の放つリリックは、やはりオカルト関連の内容だった。それらは立体的な文字群となって、彼女の前方に次々と落下した。
そして額に五芒星が刻印されたヤギの顔に、女性の体をもつ裸身の悪魔、バフォメットに姿を変えた。もちろん幻影だが、その迫力は本物だった。ヤギ頭のバフォメットが声高く「ぶおおおおー! アホめぇぇっ!」といななく姿は、実際そこに存在しているかのように思える。
少し怯んだ真一だったが、バフォメットが攻撃を仕掛けてくる様子はない。サタニックマイクが構築するラップバトル空間では、お互いの意志の強さ、メッセージ性が攻撃力となる。どうやら夜原のリリックでは、幻影の召喚こそできたものの、真一の心を貫くメッセージまでは込められなかったらしい。
甘いんだよ、クソ女がぁッ! その程度のリリックで俺を止められるわけがねーだろ! 俺にナイフを投げた行為は重罪だ! 絶対服従を誓うドM属性の犬にしてくれるわッ!
いつものように心の中で罵詈雑言を叫んだあと、真一はとどめのリリックを放った。
【俺は誰にも殺されない、それは誰もが成し遂げない、根暗女はお蔵入り。悪魔の下僕の犬野郎、この俺が下僕にしてやろう。もう辛いぞと投げ出すか、モーツァルトと投げ合うか。選べそこのマゾ野郎。くらえ、これが魔法だよ】
立体的な黒い文字として宙を飛び交ったリリックは、柔道着を着た白髪カール頭の紳士、アマデウス・モーツァルトに姿を変えた。
モーツァルトは「せいや!」と気勢をあげながらバフォメットに組みつくと、華麗な巴投げをぶちかました。柔道着姿の音楽家が悪魔をぶん投げる。すさまじい光景だった。モーツァルト先生、ごめんなさい。
「きゃあああああ!」
夜原は投げ飛ばされたバフォメットに巻き込まれて、後方の書架に叩きつけられた。十数冊の本がバサバサと落ちてくる。もちろんバフォメットも幻影なので、実際に夜原が巻き込まれたわけではない。真一が放ったリリックの魔力によって、吹き飛ばされただけだ。
本に埋もれた夜原は、放心状態のまま身動きが取れずにいた。もう攻撃してくる気配すらない。バフォメットもモーツァルトも、煙のように霧散した。バックトラックがフェードアウトしていき、ラップバトルは終了。今回も真一の完全勝利となった。
静かにバトルを見守っていたマミラダが、嬉しそうに拍手を送ってきた。
「さすが真一っ! 鋭く韻を踏んだリリックを呪文として、次々と強力な幻影を生み出す最強の召喚魔法使い! やっぱり魔王の資質があるよ! よーよー!」
「す、すさまじい召喚魔法……こ、これが魔王の力なの……?」
体の上に散らばる大量の本を払い除けた夜原が、ゆっくりと立ち上がった。ボサボサの長い髪には、雪のようなホコリが点々と付着している。別にそれを払うこともなく、じっと真一を見つめたまま、じりじりと歩み寄ってきた。
相変わらず左目は髪に隠れたまま。右目は鋭く、威圧的に真一を睨みつけている。
「な、なんだよ、もう一度勝負する気か……?」
真一がそう尋ねたときだった。
いきなり夜原は、四つん這いになった。
「魔王様、この私を足蹴にしてください! そして犬と罵ってください!」
「…………え?」
「さあ早く! この卑しい私にご褒美をください! はあはあ……」
まるで人が変わったようにハキハキと喋っている。その内容も実におかしい。
実際、人が変わっているのだ。真一が紡いだリリックの魔力によって。今の夜原は、真一の下僕であり、ドM属性の変態女になってしまっている。頬は紅潮しており、発情しているメス犬よろしく、物欲しそうに舌を出して荒い吐息までついている。
もちろんそう仕掛けたのは真一だが、バトル中は興奮状態にあったため、歯止めが効かなくなっていたのだ。バトルを終えて冷静になった今では、少しやりすぎたと反省している。
「え、えっと……」真一は困惑した顔でマミラダを一瞥した。
「本人の希望だし、犬って呼んであげれば?」マミラダは興味なさそうに読書を再開した。
「えー、そのー、い、犬?」
「ああんっ!」夜原はトロンとした目を浮かべ、心底嬉しそうな嬌声をあげた。
……これって、いいのか? いや倫理的にナシだろ。
「さ、さあっ、次は私を足蹴にしてくださいまし! さあ、さあ!」
おかしくなった夜原は、四つん這いのままお尻を高く突き上げて、ご主人様の蹴りを待っている。さすがにそれをするのは、正義の男としてダメな気がする。真一はそう思った。
「……とりあえず立ってくれるか。俺はあんたと話をしに来」
「いやです!」夜原が食い気味で否定した。「魔王様に蹴っていただけるまで、動きません!」
四つん這いのまま微動だにしない夜原の姿は、スフィンクスの石像を彷彿させた。
「ま、まあ……それじゃ、このまま話を進めるけどな。三号棟の解体話は知ってるよな? オカルト研究部は立ち退きも了承済みだっていう報告を受けているんだが、間違いないか?」
「はい! 間違いありません!」夜原は四つん這いのまま大声で返答した。
「今日はこれからヒップホップ研究部にも話をつけに行くんだ。連中さえ了承したら、一週間くらいでここを退去してもらうことになるけど、大丈夫か? もちろんオカルト研究部には、きちんと別の部室を用意するから」
「はい! ありがとうございます!」
「ところで……ほかの部員の姿が見当たらないけど、みんな今日は来ないのか?」
「オカルト研究部の部員は、卑しくも部長の私一人でございます! わんわん!」
なぜか犬の鳴き真似まで取り入れてきた。
「部員があんた一人? おかしいな、クラブ・同好会規定、第一章『部員数について』第一条の一、文化系クラブの部員数は最低五名以上とする、というルールに反しているじゃないか。それだとクラブとして認められないはずだが……?」
「実はヒップホップ研究部の面々が、形だけ入部しているのであります! その見返りとしてヒップホップ研究部がどれだけ爆音を垂れ流しても、私は関知しないという約束なのであります! わんわん!」
なるほど、校則の穴をついて存続させていたのか。もちろんそれはルール違反なので、今後オカルト研究部は同好会に格下げして、部費の支払いもストップしなければならない。まあそれは、おいおい夜原に説明しよう。今は何を言っても無駄だろうから。
それにしても……と、真一は改めて思う。この夜原の変貌ぶりはどうだ。少し前まで、あれだけ殺気をみなぎらせて俺を殺そうとしていたのに、いきなり従順になった。サタニックマイクの力は本当にすごい。
これなら全校生徒にバトルを挑んで勝利すれば、生徒会選挙の票も自由自在じゃないのか。
ふと、そんな邪悪な考えが脳裏をよぎったが、すぐさま大きくかぶりを振った。
おいおい、何を考えているんだ。清廉潔白な人生を歩んできた俺が、そんなことできるはずがないだろう。意図的な票の操作は、公職選挙法違反になる。悪魔の力を使うと、人間は堕落していくというが、俺は決してそうはならないぞ。
……でも、このマイクがあれば、マミラダを追い返すことくらいはできるんじゃないか?
真一はもう一度サタニックマイクを呼び出そうと、こっそり右手を広げた。
「何をしてるの真一?」あざとく見破ったマミラダが白い目を向けた。「一応言っておくけど、サタニックマイクは私が魔力を注入したものだから、私には効かないよ?」
「い、いや、別にそんなつもりはないぞ。ははは……」
慌てて取り繕った。やはりそう簡単に、この悪魔は追い払えないらしい。
マミラダは「ふーん」とつぶやいて読んでいた本を閉じると、
「……正直に言いなよ。今何をしようとしたの? もしも私を従わせることができたら、どうするつもりだったの? 私も真一の犬にしたかったわけ?」
部室内の空気がビリビリと震える。床に散乱していた本のページが、風もないのにバサバサと勝手めくられていく。マミラダの金色の長い髪は重力に逆らって大きく広がり、愛らしい目はうっすらと細められた。その佇まいからは、まさに大悪魔の形容がふさわしい殺気が充分にみなぎっていた。
「い、いや、本当にそんなつもりはなかったんだよ」また嘘をついてしまったことで嘔吐感を覚えるが、必死でこらえながらも強引に話題を変えた。「……た、ただ、これを使えば、選挙で票を集めることもできるんじゃないかって考えてたんだ。いや、もちろん俺はそんな不正行為はしないけどさ……」
その途端、空気の鳴動が一気に止まった。マミラダの髪も重力に従ってふわりと戻る。
「おおっ、真一も悪いことを考えるようになってきたね。うむうむ!」そしてにっこりと笑って、いつもの温和な雰囲気を取り戻した。「でも残念だけど、それはできないんだ。だってサタニックマイクで相手を従わせられる時間には、限度があるから。投票権をもっている生徒一人ずつにバトルを挑んでいる間に、どこかで別の誰かの効果は切れちゃうもん」
「え?」それは初耳だった。
「梨田とかいう人も、そろそろ効果が切れたころじゃないかな」
◇
「……ハッ!?」
ちょうどそのころ、新聞部の部室で破壊の限りを尽くしていた梨田は、マミラダの言ったとおり我に返っていた。
「……わ、吾輩は一体、どうしたんでゲスか?」
そう言って、右手に持っていたカナヅチを落とす。それで叩き割ったと思われるパソコンは完全に解体されており、マザーボードなども粉微塵になっていた。誰の目から見ても、蘇生は不可能。梨田が愛用していたパソコンは、今ここに死んだ。梨田自身の手にかかって。
愛用のデジタルカメラも同じ状況で、完全なスクラップと化していた。その脇に散らばっている細かな破片は、かつてメモリーカードと呼ばれていたものだ。今はゴミという。
「な、なんで吾輩はこんなことを……どういうわけか、生徒会長とラップバトルなんてバカなことをした挙句、自分で機材を破壊してしまうなんて。吾輩はおかしくなってしまったでゲスか? これじゃ、せっかく撮った写真が台無しでゲスよ! 吾輩のバカバカ!」
梨田は自分の頭を何度も殴りつけたあと、病院へ行こうと思った。もちろん精神状態を診察してくれる科に。
◇
「な、なんだって? そんなもん、その場しのぎにしかならないじゃないか!」
真一はマミラダに食ってかかった。
「それでも実際に、梨田って人に撮られた写真のデータを消すことができたし、今は麻里子に殺されずに済んだでしょ。ねー?」
ねー、の部分は、相変わらず真一の傍で四つん這いになったままの夜原に向けて言った。犬になりきっている夜原は、そんなマミラダに「わんわん!」と吠えて応じる。
「それは確かにそうだけど……じゃあ、効果の持続時間ってどれくらいなんだ?」
「個人差があるからなんとも言えないけど、まあ、だいたい三十分くらいかな」
「さ、三十分……」
眉間を押さえてよろめいた。三十分なんてあっという間だ。
真一は小学生のころ、「ゲームは一日三十分」というルールが決められていた。もともとそんなにゲームをしない子供だったが、テレビCMで見たタイトルが面白そうだったので、母親に懇願して買ってもらったことがある。
それは一人用のRPGだった。真一は当時からルールを厳しく守る性格だったので、ストップウォッチを傍に置いてプレイしていた。
最初のダンジョンで詰んだ。何度やっても、セーブポイントにたどり着く前に三十分が過ぎてしまうのだ。そのゲームはルールを守り通した証として、今も大切に保管している。
それはともかく、三十分で効果が切れるなら、ヒップホップ研究部の連中を三号棟から退去させることも不可能だ。正気を取り戻されたら、立ち退き話も白紙に戻るのだから。
「よ、よくこんなもので、世界中の人間を屈服させられるとか言えたな!」
「なんでさ。三十分だけでも、その間に真一が『自殺しろ』っていう意志をぶつけたら、その人は本当に自殺するんだよ。使い方次第では、世界征服だってできるじゃん?」
さすがは悪魔。恐ろしいことを平然と言ってのける。そして本当にそれができてしまうのがサタニックマイクなのだ。極端な話、核ミサイルの発射スイッチを持っている人間に「世界を滅ぼす」という思想をもってバトルを挑めば、それを押させることだって可能となる。
ちょっと待てよ、真一はふと疑問が浮かんだ。
それができるのは、あくまで自分がラップバトルに勝利したときの話だ。今のところ全勝しているが、真一自身がバトルに負けたらどうなるのかは、まだ聞いていない。
マミラダの説明は、肝心なところが抜けまくっていた。改めて尋ねてみる。
「ラップバトルはお互いの意志のぶつけあいだからね。真一が負けたらもちろん、相手の意志を受け入れてしまうことになるよ。その効果の持続時間も、やっぱり三十分くらいかな」
つまり梨田とラップバトルをしたときの例だと、真一は「写真データを消せ」という意志をもって戦い、梨田は「写真データを公開する」という意志をもって戦った。真一が負けていたら、自ら写真の公開を了承する形になっていたわけだ。
ということは、「真一を殺してマミラダを自分のものにする」という意志をもって戦った夜原に負けていれば――考えると背筋に冷たいものが走る真一だった。
「まったく……制限時間といい、負けた場合のことといい、最初から全部きちんと言っておいてほしかったぜ。さすがにもう伝え忘れはないよな?」
呆れながらそう言うと、マミラダは妙な含みをもたせて、こう返してきた。
「伝え忘れはないけど、言ってないことならまだあるかな」
「なんだそれ? だったらちゃんと言えよ」
「んー、別にたいしたことじゃないんだけどね」
「小さなことでもちゃんと説明しろ。消費者契約法には『不利益事実の不告知』っていう項目があってだな。つまり契約時に故意に情報を隠すと、契約の取り消しに……」
「だって、本当にたいしたことじゃないよ?」
「じらすな。早く言え」
「サタニックマイクの正当な持ち主になった真一は、バトルをすればするほど、契約者の私に魂を取られちゃうんだ」
あまりにも平然と言われたため、聞き間違いかと我が耳を疑った。
「……今なんて言った?」
「だからぁ、真一がサタニックマイクを使えば使うほど、その魂は私のものになるの。やっぱり悪魔は、人間の魂をもらってなんぼの商売だから。儲かりまっかーってね」
真一は呆然と立ちすくんだまま、何も言葉を発せない。
マミラダは黙りこくっている彼が納得したと考えたのか、近くの椅子に腰かけて読書を再開した。夜原は相変わらず、真一の傍で四つん這いになったままだ。蹴ってほしそうな顔で。
その光景が一分くらい続いただろうか。立ちすくんでいた真一は、唐突に笑いだした。
「はははっ、それもデビルジョークだよな。冗談きついぜ」
「本当だよ? デビルジョークはもっと面白いもん」
「いやいや、お前は今朝こう言ったじゃないか。悪魔と契約しても魂は取らないって」
「うん、契約した『だけ』なら取らないよ。使えば使うほど、見返りがあるのは当然じゃん」
ようするに、クレジットカードと同じ理屈だ。作るだけならタダ。使って初めて金銭が徴収される。「ほら、別にたいした話じゃないでしょ」
「めちゃくちゃ大事な話じゃねーかクソチビがァッ!」思わず汚い言葉で叫んだ。「契約の取り消しを訴える! これは消費者契約法違反だ! クーリングオフだァッ!」
マミラダは椅子に座ったままため息をつくと、静かに本を閉じた。
「もう、うるさいなぁ。魂を取るって言っても、厳密にはまだ仮押さえ段階だよ。実際に徴収するのは、真一が死んでから」
そして右の手のひらを上に向けると、そこに小さな砂時計を出現させた。フラスコを二つくっつけたようなポピュラーな形の砂時計だ。上部分には大量の砂が溜まっているが、下部分にはあまりない。砂の流れは現在止まっていた。
なんだそれは、と息巻く真一にそれを見せながら、マミラダは面倒くさそうに続けた。
「この砂時計の砂が真一の魂を示しているの。まだたくさん砂が残っている上部分が、真一の魂の現在値。少ししかない下部分は、私がもらう予定の魂の現在値。真一がサタニックマイクを使うたびに、少しずつ上から下へ砂が流れ落ちてくるの」
マミラダの説明によると、上部分にある砂がすべて下に落ちると、完全に魂を取られた状態になるらしい。そうなると真一の魂は肉体から切り離されて、完全にマミラダのものとなる。
もちろん肉体から魂が離れることは、死を意味する。
普通、寿命で死んだ人間の肉体からは、魂が自然に分離する。そういった魂は霊界を経由して別の肉体へ転生するらしい。しかし生きている間に悪魔に取られてしまった魂は、霊界に行かず、そのまま魔界へ連れて行かれるそうだ。そうなったら転生もできない。
「……というわけ。私は今回の召喚で四度目って言ったでしょ。過去三人の魂は今、魔界の私の家で平和に暮らしてるよ。セカンドパックもそこにいるんだ。彼には庭師として働いてもらってる。ほかの二人は残念ながら、ペット状態なんだけどね。あははっ」
マミラダが真一の魂を測る砂時計を宙に放り投げると、それは手品のようにパッと消えた。
「……じゃあ砂時計の砂が全部流れ落ちる前に、俺が寿命で死んだらどうなるんだ?」
「いくら砂が下に溜まっていても、先に寿命で死なれたら魂が取れなくなっちゃう。そのときは残念ながら、真一の魂を魔界へ連れて帰ることができなくなるってわけ。だからお願い。たくさんサタニックマイクを使って、寿命がくる前に私に魂を全部ちょうだい?」
「やるわけねーだろ!」
ようするにサタニックマイクを使えば使うほど、魂は仮押さえ状態となり、限界が来れば、マミラダに魂を取られて死んでしまう。限界の前に使用をやめれば魂は取られることなく、普通に天寿をまっとうして、次の人生を始めることができるというわけだ。
「悪魔も辛いんだよ。与えた力が使用限度額を超えなければ、契約者の魂を取ることはできずに、踏み倒されちゃうんだから。ひどい話だよねー?」
真一はそれを聞いて、少しだけ安心した。すでに二度もサタニックマイクを使ってしまったが、その程度ならまだマミラダは、完全に魂を取ることができないらしい。
「なるほどな……ちょっと焦ったが、ようするに、もう二度とサタニックマイクを使わなければいいだけの話だ」
「わかってないなぁ。どうして私がわざわざ、魂の話をしてあげたと思う? もう二度と使わないって言いながらも、人間って心が弱いから結局は『あと少しなら大丈夫』とか言って使っちゃうんだよ。そしていつの間にか限度額を超えてしまって、悪魔に魂を取られちゃう。だから別に、教えても問題ないの。むしろ、使わないって言っている人が悪魔の誘惑に負けてしまうところが見たいから、あえて教えてあげることもあるんだよ」
「俺はそこらの人間とは違う。もう絶対に使わん」
「どうかなー? 私は真一と結婚するって言ったよね。それはつまり、何があっても真一から魂を取って、魔界へ連れて行くってことだよ。この意味がわっかるっかなー?」
やたらとウザい口調でそう言ったマミラダは椅子から立ち上がると、冷蔵庫で偶然ゼリーを見つけたイタズラ小僧のような忍び笑いをしてみせた。
「ど、どういうことだよ……?」
真一がそう言ったとき、オカルト研究部の部室の外から、騒がしい声が聞こえてきた。
十数人ほどの男たちの声だ。声は徐々に三号棟のほうへ近づいてきている。
「ひょっとして、部室を留守にしていたヒップホップ研究部が戻ってきたのかな?」
マミラダのつぶやきに、四つん這いの夜原が「そうだと思います、わん!」と吠えた。
それを聞いて真一は深いため息をついた。
「……とりあえず、サタニックマイクを使って連中を三号棟から追い出す作戦は、白紙に戻すしかないな。俺はもう二度とあのマイクを使わないし、仮に使ったとしても、その効力は三十分で切れる。この作戦は最初から無理があったんだ」
生徒会役員の前では「俺が連中を説得してこよう」と偉そうなことを言ったものの、やはりまた別の役員に説得を頼み直すしかない。そんなことを考えていたときだった。
マミラダがすーっと大きく息を吸い込んだと思いきや、
「ええーッ! 生徒会長の音川真一くんは、ヒップホップ研究部を相手に、フリースタイルのラップバトルを挑もうとしているんですかー!?」
三号棟全体を震わせるかのような大声をあげた。
「お、おい、お前、急に何を言い出すんだ……!」
真一が小声で咎めるも、マミラダは止まらない。
「なんですって! ヒップホップ研究部は、くそワック(超ダサい)なラッパーの巣窟!? あの程度の連中なら、自分のラップのほうが圧倒的にすごいですって!? 生徒会長、それはいくらなんでも言い過ぎです! 連中に聞こえたら大変ですよ!」
その大声は外まで届いたらしい。
「もう聞こえてんだよゴラァッ! すぐそっちに行くから待ってろ、チェケラー!」
外からこれまた大きな怒声が返ってきた。間違いなくヒップホップ研究部の面々だ。
真一はようやくマミラダの考えを悟った。
マミラダは、真一がサタニックマイクを使わざるを得ない状況を無理やり作り出そうとしているのだ。そして限度額を超えさせて、真一から魂を取る。そのまま魔界へ連れ帰って、強引に結婚。それが狙いなのだ。
ちくしょう、なんて悪魔だ! 口の中に練りワサビを全部ぶちこんで、ガムテープで塞いでやりてーよ!
考えている間にも、ヒップホップ研究部の面々は口々に怒号を吐きながら、三号棟の階段をガンガンと乱暴に踏み鳴らして駆け上がってくる。
「や、ヤバい! 本当にこっちに来る! とりあえずお前は姿を消せ!」
真一に促されたマミラダは「ほいほーい」と軽いノリで透明化した。オカルト研究部のドアが荒々しく開かれたのは、それとほぼ同時だった。
開かれたドアの向こうには、十数人の男たちがずらりと並んでいた。校内にも関わらず、やはり全員が私服。サイズの大きな服を着こなすBボーイファッションの集団だった。
先頭にいるのは、昨日の放課後に廊下で出会ったヒゲ坊主と、巨漢キャップだ。
「よう生徒会長。俺たちにフリースタイルのラップバトルを挑みたいんだって? 相当上等、暴動濃厚。チェケラー」
「い、いや、俺は別にラップバトルをするなんて……」
真一が言い終わるのを待たず、ヒップホップ研究部の面々は、ずかずかとオカルト研究部の部室内に踏み込んできた。
「ああ? オメェが言ったんだべ? 俺たちとバトルしたいってよぉ?」
「しかも俺たちのことを、ワックって言ったらしいな。それってディス(けなし)だよなぁ? あんたは俺たちをディスったんだよなぁ?」
すでに臨戦態勢に入っているヒップホップ研究部の面々は、「それじゃ、生徒会長を俺たちの決闘場へお連れしようぜ!」と、全員で胴上げするかのように真一の体を担ぎあげた。
「ちょ、ちょっと待てって! 俺の話も聞いてくれ!」
「言いたいことはマイクで語れ。チェケラー」
「わんわん! 魔王様ファイトです、わん!」
緊迫した空気のなか、相変わらず四つん這いの夜原が、緊迫感のない声で言った。
◇
三号棟のすぐ脇には、かつてハンドボール部が屋外の練習場として使っていた広場がある。現在は廃部になっているため、そこは誰でも使える多目的広場になっていた。
とはいっても、その広場は三号棟のすぐ脇にあるため、普段は誰も近づかない。もっぱら、ヒップホップ研究部専用の遊び場、もとい決闘場となっていた。
今日もここで、ラップバトルという名の決闘を繰り広げる両雄がいた。真一とヒゲ坊主だ。
しかしラップを披露しているのはヒゲ坊主のみ。サタニックマイクを使っていない真一は、ヒゲ坊主の正面でただ突っ立っているだけなので、およそ決闘と呼べる代物ではない。
【ヘイYO。俺たちは三号棟から立ち退かない、何があっても屈しない。権力振りかざす生徒会長、テメェに刀を振りかざそう。俺のライムでぶった斬る。慈悲のねぇ仏陀もぶった斬る。学院なんてマザーファッキン】
ギャラリーのヒップホップ研究部メンバーたちは、ヒゲ坊主のラップに合わせて口々に歓声を上げていた。なかには、まるで反撃する素振りがない真一への野次も混じっている。
「どうした生徒会長! あんた、俺たちより圧倒的にラップがうまいんじゃねーのかよ!」
「さっきからずっと突っ立ってるだけじゃねーか。だせぇ野郎だぜ!」
なんとでも言え、と真一は思っていた。サタニックマイクはもう使わないと決めている。マミラダの思惑通りになってたまるか。こんな手に引っかかる俺ではないのだ。
真一はまったく口を開かないため、ずっとヒゲ坊主のターンが終わらない。延々と彼のラップを聞かされるばかりだ。ヒップホップが嫌いな真一にとって、それはあまりにも退屈な時間だった。
一方的にラップを披露していたヒゲ坊主だったが、やがてそれを中断して嘲笑を浮かべた。そしてバックトラックを流していたラジカセのスイッチを切る。これでバトル終了。勝敗は誰の目から見ても明らかで、一度もラップを披露しなかった真一の完全敗北だ。というか、最初から勝負にすらなっていない。
「へへっ、俺のラップにビビって、反撃もできないってか。話にならねーな。チェケラー」
「は、はは、返す言葉もない……」
口ではそう言いながらも、真一は胸中で嘲笑を浮かべていた。
けっ、何を言っているんだ。メッセージ性も何もないラップを披露しやがって。何が「学院なんてマザーファッキン」だよ。汚い言葉を吐いているだけで、知性のかけらも感じられん。サタニックマイクのおかげとはいえ、ヒップホップなんかに興味のない俺のほうが、まだマシなラップができるぜ。
「あーあ、ずいぶん呆気ない決着だったなぁ」ギャラリーの中にいた巨漢キャップが、呆れた口調で言った。「まあ生徒会長なんて、こんなもんだろ。口だけは達者なんだから」
それをきっかけに、ヒップホップ研究部の面々は一斉に笑い出した。
「ぎゃははは! そりゃそうだろ、こんな奴にラップができるはずねーもん!」
「生徒会長ごときが、俺たちにラップバトルを挑むなんて、百年早いんだよ!」
真一は「やれやれ」と肩をすくめてみせると、
「さ、さてと。勝負も終わったことだし。そ、そろそろ俺は帰らせてもらおうかなー……」
そう言って踵を返した。ずいぶん時間を無駄にしてしまった。さっさと日課の見回りを終えて帰ろう。急がないと下校時間に間に合わなくなる。
真一が歩き出したとき、ヒゲ坊主がその背中に向かって、こんなことをつぶやいた。
「マジで拍子抜けだぜ。自分でラップバトルを挑んできたくせに、まさかルールすら守れねーとはな。チェケラー」
連中に何を言われてもまったく気にならなかった真一だが、その言葉だけは胸中に深く突き刺さった。それは両足にも楔となって打ち込まれ、ぴたりと歩みが縫い留められる。
「…………ちょっと待て。俺がルールを守ってないだと?」
振り返った真一がそう言った。その顔にはもう、不良に対するいつもの気弱な作り笑いがない。対照的にヒゲ坊主は嘲笑を浮かべたままだった。
「ああ、そうだぜ。ラップバトルっていうのはな、お互いが交互にリリックをぶつけあうのがルールなんだ。それなのにテメェは、まったく反撃してこなかったじゃねーか。口だけ野郎はさっさと消えろ。チェケラー」
別に真一は彼らにラップバトルを挑んでいない。無理やりその形にもっていったのはマミラダだ。だから本来なら、これも気にする必要はない言葉である。
しかし真一にとって「生徒会長がルールを守らなかった」と言われることは、これ以上にない侮辱であり、屈辱だった。だからこそ、こんな言葉が自然と出てしまったのだ。
「……そこまで言うなら、ラップバトルのルールに従って勝負してやってもいい」
「だからもう決着はついただろ。あんたの不戦敗だ。俺のラップにビビって何もできなかった奴が、笑わせるんじゃねーよ。チェケラー」
ヒゲ坊主のそんな言葉を合図に、残りのメンバーたちが腹を抱えて大笑いを始めた。全員が例外なく真一を馬鹿にしている。
「だったら賭けをしないか?」真一はヒゲ坊主を見つめたまま冷静に言った。「俺があんたに勝てば、ヒップホップ研究部は潔く三号棟から出て行く。俺が負けたら、生徒会は二度とあんたたちに関与しない。三号棟の解体も中止するよう学院側に訴えてやる」
さすがは学院の平和をいつも考えている生徒会長。怒りに任せて勝負を挑むだけの愚者ではなく、とっさに機転が効くクレバーな男だった。こういった約束を取り付けたら、サタニックマイクの効果が三十分で切れようと、連中を追い出すことができると思い至ったのだ。
そして期待通り、ヒゲ坊主は真一の提案に乗ってきた。
「へへっ、そこまで言うならやってやるよ。生徒会長なんだから、約束はちゃんと守れよ?」
ヒゲ坊主が自分のワイヤレスマイクを片手でくるくる回しながら言った。
サタニックマイクの限度額までは、まだまだ余裕がある。あと一回、ヒゲ坊主一人に使うくらいなら大丈夫だろう。マミラダの思惑通りになるのはシャクだが、サタニックマイクの使用はこれが最後。ここでヒゲ坊主を仕留めたら、もう絶対に使わない。改めてそう決意した。
「ああ、お前らこそ約束は絶対に守ってもらうからな」
真一は右手をズボンのポケットに突っ込んだ。そして小声で「ノイズを取る、このマイクバトル」と唱える。ポケットの中でサタニックマイクが出現した。ゆっくりそれを抜き出して、戦いの構えを取る。
「お? 自前のマイクまで持ってやがったのか。意外とやる気じゃねーか。チェケラー」
不敵に笑うヒゲ坊主に向かって、真一は強気な態度を崩さずに言った。
「さっきのバックトラックはあんたが決めたんだから、今度は俺が決めてもいいよな?」
「いいぜ。音源はどこにあるんだ?」
「それもポケットの中にある。今から再生するぞ」
言いながら真一は、サタニックマイクのドクロの装飾をヒゲ坊主に向けた。
赤く光るドクロの両目がヒゲ坊主の網膜に映った途端、どこからともなくバックトラックが流れ出した。サタニックマイク発動。戦闘準備は整った。
真一とヒゲ坊主を取り囲むヒップホップ研究部の面々が、一斉に歓声を上げ始める。
「生徒会長さんよー、本当に俺たちよりも、すげーラップができるんだろうなぁ?」
「くだらねーラップをかましたら、ぶっ殺すからな!」
高まるボルテージのなか、先行を取ったのはヒゲ坊主だった。
【ヘイYO、聞こえるか生徒会長、あいまみえるかこの俺と。谷間見えるかそこのギャル、ガニ股歩きのそこのサル。サルはテメェだ生徒会長。あんたのラップはぜひ拝聴。だけど、サルにラップはできやしねぇ。口だけ達者はマジで死ね】
ヒゲ坊主が紡いだリリックは、立体的な黒い文字となって中空に出現した。それらは真一の周囲にドスンドスンと落下すると、無数のサルに姿を変えた。
「お、おい、なんか生徒会長の周りにサルの群れが見えるんだけど……?」
「MCケンジのリリックが、それだけ強烈だってことじゃねーか? プチョヘンザー!」
ギャラリーの面々が騒ぎ出した。MCケンジというのは、ヒゲ坊主の通称らしい。
ヒゲ坊主のラップは、まったく真一の心に響かなかった。メッセージ性という名の攻撃力は皆無。召喚されたサルたちも真一の周囲をぐるぐると飛び回っているだけで、何かを仕掛けてくる様子はない。
そして次は真一のターンだ。普段なら決して口にできない連中への鬱憤をバックトラックに乗せて、今度こそ逆襲を開始する。
【サルはテメェだ、くそヤンキー。ルール無用のアホモンキー。学院で私服、ただのガキ。言っても直らん恥さらし。三号棟は動物園、放物線で飛んでいけ。ラッパー真一のアッパーカットで、サッカーボールのように飛んでいけ】
やはり立体的な文字となって出現したそのリリックは、真一の周囲に群がっていたサルたちの前にそれぞれ落下する。そして次々とボクサーの格好をした無数の真一自身の姿に変化していった。まるで分身の術でも使ったかのような光景だ。
召喚されたボクサースタイルの真一の幻影たちは、軽くフットワークを取りながら、各自の前にいるサルたちに、鋭利なアッパーカットを放った。サルたちは全員吹っ飛んでいく。放物線を描くサッカーボールのように、空の彼方へ。
「なな、なんだこれはぁッ!?」
「せ、生徒会長の分身が現れて、サルたちを一気に吹き飛ばしたぁッ!?」
口々にそう叫ぶギャラリー同様、対戦相手のヒゲ坊主もうろたえていた。真一が予想以上に強烈なラップで切り返してきたからだ。
ヒゲ坊主はうろたえながらも、自分のマイクを握り直して、さらに反撃してきた。
【さ、三号棟は俺たちの居場所! だから言いましょ、ここは格好の場所、テメェは場違い!】
すぐさま真一もラップでアンサーを送る。
【三号棟はお前らの死に場所。読めよ教科書、ここは学校の場所、テメェら勘違い】
即座に切り返されたことで、ヒゲ坊主のラップは止まってしまった。ここぞとばかりに真一は追い討ちを浴びせる。【私服厳禁、土足厳禁、ヒゲも厳禁、タカり厳禁、サボり厳禁、バイク厳禁、威嚇厳禁、ケンカ厳禁、遅刻厳禁。下校時間無視、騒音苦情無視、学院行事無視。三号棟に滞在するテメェらの十二の大罪。くれてやるよ今日中に引導、果たすのはそう十二神将】
真一の韻を踏んだリリックという呪文によって、仏法を守護する十二体の巨大な仏像、十二神将が召喚された。
それぞれの身の丈は三メートルほどあるだろうか。怒りに顔を歪める屈強な仏像群は、校則の守護神こと真一に命じられるまま、ヒップホップ研究部を踏み潰すように行軍を始めた。
「う、うわああああッ!?」「ひ、ひいいいいッ!?」
バトルを見守っていたヒップホップ研究部の面々は、人間に追い回されるアリの群れのごとく、一目散に逃げ出した。対戦相手のヒゲ坊主は腰が抜けてしまったのか、その場でペタンと尻餅をついてしまい、仏法……ではなく校則を守護する十二神将を唖然と見上げていた。
真一のラップはそれでも止まらない。とどめのリリックを紡ぎ出す。
【校則違反者は取り締まる。風速百メートルで吹き飛ばす。校則を守れば、約束された安息。テメェもヒゲを剃れ、さっそく。学院の掟はマジ鉄則】
魂の叫びが充分に詰め込まれたラップは、そこに風速百メートルの強風を呼び起こした。
「うぎゃあああああッ!?」
ヒゲ坊主はその強風を受けて吹っ飛ばされた。もちろんそれも幻影なので、実際は真一の魔力が込められたラップによって、吹き飛ばされているのだ。
同時にどこからともなく流れてくるバックトラックが止んだ。十二神将の幻影と共に、真一の手にあるサタニックマイクもゆっくりと消えていく。ラップバトルの決着がついたのだ。
先ほど逃げ出したギャラリーたちは、広場の端に林立する樹木の陰からこっそり様子を伺っていた。
「な、なんだよ、あいつのラップは? エグすぎるパンチライン(印象的なリリック)だったぞ……?」
「ここまでイメージがはっきり見えるほど、強烈なリリックを繰り出す奴は初めてだ……」
ヒゲ坊主は数メートル先で転がっていたが、やがてのろのろと身を起こすと、
「うおおおー! 俺はなんて悪い奴だったんだー!」頭のバンダナを取って、Tシャツも脱ぎだした。「決められた校則を守らないなんて、俺にこの学院の生徒を名乗る資格なんてねぇ! ヒゲだってむしり取ってやる! チェケラー!」
私服をすべて脱ぎ捨てて、ブリーフ一丁という哀れな姿になったヒゲ坊主は、自らの顎に手をかけて、ぶちぶちとヒゲをむしり出した。その様子は狂人そのものだ。
「……俺の勝ちだな。それじゃ約束通り、お前らは三号棟から出て行って……」
真一が言い終わるより早く、ヒゲ坊主は大声でかぶせてきた。
「もちろんだ! 校則を守らない俺たちはゴミだ! 今すぐ出て行くさ、チェケラー!」
「お、おい、勝手に決めるな、MCケンジ!」
ヒップホップ研究部のメンバーたちが、ヒゲ坊主に詰め寄った。しかしサタニックマイクの魔力下に落ちているヒゲ坊主は、「ええい黙れ!」と大声で制する。
「俺たちは生徒会長と約束しただろ、負けたら三号棟から出て行くってな。校則を守れば約束された安息か……素晴らしいリリックだ。俺の完全敗北だぜ、チェケラー」
ヒゲ坊主は完全に真一のラップ、もといサタニックマイクの魔力に心酔していた。もちろんその魔力にかかっていない残りのメンバーは納得しない。納得はしないが、真一にラップバトルを挑む度胸もないようだ。それぞれ遠慮がちに「次はお前が生徒会長と勝負しろよ」「いや、お前がやれよ」と牽制しあっている。
さすがにこれ以上、サタニックマイクで勝負するわけにはいかない。頼むから、おとなしく引き下がってくれ。真一が切にそう願っているときだった。
ぴゅるりー。
どこからともなく口笛の音が聞こえてきた。まるで陽気な裁判官が「静粛に」と打ち鳴らす小槌の代わりに吹いているようで、その場にいるすべての人間から声と物音を奪った。
真一を含めた全員が、静かにあたりを見回して音の発信源を探っていると、
「あそこだ!」
巨漢キャップがひときわ背の高い樹木を指差した。その樹木から伸びる太い枝の上には、幹に背を預ける形で一人の男が寝そべっていた。
その男は奇妙、というか奇抜な格好をしていた。テンガロンハットにポンチョ姿、腰にはガンベルトを巻いている。まるで西部劇に出てくるガンマンだ。ただし西部劇好きの人間でも、その姿を見ると非常に不愉快になるに違いない。ガンベルトに収められているのはリボルバーではなく、ワイヤレス型のマイクなのだから。時代設定がカオスすぎる。
ガンマンは口笛を止めると、そのまま枝から飛び降りた。ポンチョがふわりと舞う。そして特撮ヒーローのように片手をついて優雅に着地すると、ポンチョを翻して不敵に笑った。
「しかと見届けさせてもらったぜ。あんたはマイクを武器にして戦う現代のガンマンだ。この学院に、俺ッチと肩を並べるガンマンがいたとはねぇ。荒野に向かってバキュン」
そう言ったガンマンは、ゆっくりと真一に歩み寄った。
……とうとう現れやがったな、学院の悪玉菌め。真一は心の中で毒づいた。
「し、司馬坂さん! いつからそこにいたんですか!?」
ざわめくヒップホップ研究部のメンバーたちに、ガンマンは拳銃をかたどった指を向けた。
「ジャガイモは地面に成るもの、そして俺ッチは木の上にいるものさ。摩天楼にドキュン」
意味不明なことを口走るガンマン。この男がヒップホップ研究部の部長で、鏡波学院においてもっとも危険と称される男、クレイジーホースの司馬坂軍馬だ。
不良集団ヒップホップ研究部のリーダーを名乗るくらいだから、最初は誰もが屈強で強面のBボーイを想像する。しかしその正体は、西部劇かぶれのコスプレ野郎。これを知ったときの真一も驚愕したものだ。
とはいっても司馬坂は「一分間でパトカーを五台も燃やす」「ケンカを売ってきたボクサーを拳のみで倒す」など、数々の危険な伝説を残している。一見ただのコスプレ野郎に見えても、誰も手をつけられない荒くれ者という点は間違いない。
「すいません司馬坂さん! MCケンジがこの男にラップバトルで負けてしまって……」
巨漢キャップがそう言うと、司馬坂は静かに頷いた。
「全部見てたぜ。MCケンジが生徒会長さんに負けたら、ここを立ち退くっていう話も聞いたさ。俺ッチのいないところで勝手な約束をしやがって。まったく、お前さんらときたら、ジャンケンで最初はグーって言ってるのに、パーを出してくるくらい悪い奴らだねぇ」
わけのわからない発言をする司馬坂に対しても、ヒップホップ研究部のメンバーたちは一斉に「すいません」と頭を下げるばかりだ。
サタニックマイクの影響下にあるヒゲ坊主だけは「でも司馬坂さん、約束は約束です!」と食い下がった。司馬坂はそれも手で制する。
「わかってるさ、MCケンジ。お前さんは生徒会長さんと誇り高い決闘をして負けた。ここで俺ッチが異論を唱えると、お前さんがピエロになっちまう。でもサーカス団からのスカウトは断ってやるから安心しろ」
何を言っているんだ、こいつは。真一は司馬坂の言動の一つ一つがまったく理解できなかった。やはり関わりたくない相手だ。しかしせっかくラップバトルで勝利した以上、ここで引き下がるわけにもいかない。
「ひ、ヒップホップ研究部の部長、司馬坂さんだな? 聞いていたなら話が早い。や、約束通り、あんたたちは三号棟から立ち退いてもらう……ぞ?」
真一がビクビクしながらそう告げると、司馬坂は素直に「わかっているさ」と返答した。
「ただし生徒会長さんよ。さっきの決闘は、部長の俺ッチの管轄外だったんだ。だからこそ、俺ッチたちの立ち退きには、一つだけ条件を飲んでもらいたい」
「い、言っておくが、代わりの部室を用意しろ、というのは無理だからな。もう、どこも部室として使える場所がないんだ」
本当は部室にできる空き教室なら、たくさんある。しかし、ここで甘やかしてはいけない。念願だったヒップホップ研究部の駆逐まで、あと一歩なのだ。
「ちょっと待てよ生徒会長!」巨漢キャップが口を挟んだ。「代わりの部室も用意してもらえないってことは、実質上クラブの解散じゃねーか! 司馬坂さん、それでいいんすか!?」
司馬坂は「ふう」と大袈裟にため息をつくと、
「生徒会長さんがそう言うんだから、仕方ねーだろ。俺ッチたちの活動は学院の外でもできるじゃねーか。ただし俺ッチはヒップホップを愛する者として、どうしても立ち退き前に学院内でやりたかったことがあるんだ。それを了承してもらえるなら、潔く立ち退くさ」
「なにそれ、なにそれ? 面白そう!」
突如、広場にそんな声が響き渡った。
姿を消したまま、成り行きを見守っていたマミラダの声だ。今までおとなしくしていたくせに、司馬坂の言う「ヒップホップを愛する者として、どうしてもやりたいことがある」という言葉に反応してしまったらしい。
「今、何か声がしたような……?」ヒップホップ研究部の面々が、あたりを見回す。
「きっと北風の声さ」司馬坂が悟りきった顔で言った。
真一はマミラダの声を無視して咳払いをすると、司馬坂に向き直った。
「と、取引なら応じないぞ。どうして俺があんたたちの要求を……」
そこまで言ったとき、真一は続きの言葉と一緒に、呼吸まで止まってしまった。
透明化していたはずのマミラダが、司馬坂やヒップホップ研究部メンバーたちの後ろで、姿を堂々と見せていたからだ。「話くらい聞いてあげてもいいじゃん」と書かれたスケッチブックをカンペのように掲げている。
「バ、バカ、姿を見せるな!」
思わずそう言ってしまったことで、司馬坂たちが一斉に振り返った。今度は心臓まで止まりそうになる。
案ずるなかれ、マミラダは寸前で姿を消した。
「へえ、あんたは北風と会話ができるのかい。クールだねぇ」司馬坂が口笛を短く吹いてみせた。「で、どうなんだい? 俺ッチたちの立ち退き条件を飲んでくれるのかい?」
司馬坂たちが真一に向き直ると同時に、またしても彼らの後方で、スケッチブックを持ったマミラダが姿を現した。スケッチブックには「真一が話を聞いてあげないなら、私が代わりに聞いてあげようかな」と書かれていた。
真一は心底脱力した。ここで司馬坂の提案を受け入れなければ、マミラダは悪魔の姿を全員の前にお披露目するだろう。そうなったら、さらに面倒なことになる。
どうやら真一には、司馬坂の出す条件とやらを飲む道しか、残されていないようだった。